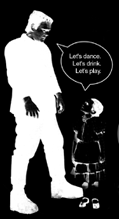
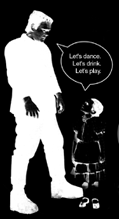
◆ビジュアル・コミュニケーションの基本的な意味。
○視覚の介在するコミュニケーション”である。
人間は視 覚を持った動物であるから、人間同士のコミュニケーションに視覚が介在するのは当然である。
◆人格情報。
○現在人間同士のコミュニケーションでもっとも大きな 役割を果たしている視覚情報は『ファッション』であろう。
職務や社会的役割からやや離れて多彩な服を着られるようになり、自分の価値観を表現する情報、いわば『人格情報』を身にまとっている。
◆感情情報
○最近の子供はたちは、当たり前のように器用にマンガを描くことが多い。子供たちは至るところでマンガを描く。
マンガやアニメは単純な線で豊かな感情を表現する。
始まりは単なる模倣であろうが、それらを『部品』として、コ ラージュのように自分の情を組み立てることにより、何らかの『感情情報』を伝達する手段にまで発展していると考えるのが妥当ではないだろうか。
◆ビジュアル・コミュニケーションは画像や映像を入力、加工、伝達する手段の一つを通じてさらに深化すると考えられる。
○通信技術や映像技術の発達により、人 間がメディアというフィルターを介してコミニケーションを行うよ うになった。テレビやビデオを当たり前のように見て育った世代にとって、人工的な視覚体験はもはや感 覚器官の一部のようなものである。
・映像を、一方 向のマスメディアだけでなく双方向のコミュニケーションでも活用しようと考えるのは自然の流れである。
そして、メディアを介したコミュニケーションは、時間をかけて作り出した情報を不特定多数にコピーして伝達する方向へと進んでいく。
・不特定多数による通信は無線の時代から存在したが、視覚を介した不特定多数による通信のはじまりはパソコン通信である。
パソコン通信は文字情報しか扱えないが、チャットというリアルタイムのコミュニケーションの場を中心に、文字を使って感情を表現する『顔文字』が出現した。
顔文字において文字は文字としての意味を失い、単なる輪郭として『感情情報』を伝えるための道具となっている。
※パソコン通信の一般への普及と時を同じくして1993年あたりから若者の間ではポケットベルがブームになり、文字を使って『感情情報』を伝える役割を果たしていたのが興味深い。
・パソコン通信はインターネットへと発展し、文字と画像がミックスした『人格情報』としてのホームページ、日々の『感情情報』を伝えるウェブ日記やウェブチャットへと深化した。
・電子メールも従来は文字のみでやりとりするのが一般的であったが、ここ2〜3年の間に画像を添付するのが一般的になってきている。
・現在の状況に至るまでにはいくつかの技術的革新があった。
⇒画像の入力手段として
…デジタルカメラの普及、コンピューターの処理速度の向上とユーザ・インターフェースの改善など。
・これらにより、顔を変形したり色を変えるといった『感情情報』を表現するための画像の加工('EE = emotion effect')が容易かつ効果的になった。
⇒⇒⇒そしてインターネットという場で不特定多数に発信する。
・⇒⇒⇒ ⇒⇒⇒
の流れが一つにつながる。
・また、すでに存在しているキャラクターや素材集をコラージュのように組み合わせることにより、自分の個性を表現するための『人格情報』の生成も容易になった。
・ 同じ時期に若者の間では使い捨てカメラ、プリクラ、ポラロイドといったブームが起こっている。
写真には撮影後にペンで落書きのような書き込みがされ、共通の思い出という『感情情報』の共有が図られている。
・一方でプリクラはあ らかじめ用意された『人格情報』であるところのキャラクター商品と融合していった。
※若い世代の人達が常にプリクラを身につけて自分の身分証明書として使っているように、これらの映像の社会的役割が衣服と酷似していることに注目されたい。
→→→キャラクター商品をファッションとして身につけるのが流行っているのは、当然の流れなのである。
・通信においては、数年以内に画像に加えて映像が一般的に使われるようになるだろう。
(静止画ではなくて、アニメーションなどの動画。メディア・フラッシュで作成できるような。)
・ことばの世界において、概念は同一の文化圏ではかなりの部分が共通化されてる。
微妙なニュアンスが共有できて初めて文章の表現技巧が成り立つ。
一方画像や映像においては、抽象化した 概念としての教育が行われているわけではないから、記号を共通化するためのコンセンサスが存在しているわけではない。
・しかし、マンガやアニメのような抽象化した視覚的感情表現に慣れた世代にとっては、顔文字を見て「(^_^)」が『笑い』、「(;_;)」が『泣く』という感情であると解釈するのに抵抗が少ない。
・今日では数多くの顔文字が存在しているが、それらを共有できるようになっ た背景にはマンガやアニメを 浸透させたマスメディアの影響が大きい。
それゆえ一般的な『感情情報』や『人格情報』は先の顔文字やサンリオのキャラクターに代表されるような ステレオタイプ的な表現となり、それとは別に特定のコミュニティの中だけで通用する『感情情報』や『人格情報』が局地的に存在する状況になっていくだろう。
○ビジュアル・コミュニケーションが発達する社会的背景
・人間が良くも悪しくも個へ向かうという社会背景に加えて、携帯電話やインターネットなどの通信インフラの普及を原動力として、加速度的に人間関係が拡散化していることが挙げられる。
従来に比べてはるかに多くの他人と接触する一方で、それぞれとの接触はどんどん希薄になる。
そのような状況で人間関係を維持するために、不特定多数を対象に瞬時に『感情情報』や『人格情報』が伝えられるビジュアル・コミュニケーションが必要とされる土壌がある。しかし、パソコンの画面に向かって「(^_^)」という顔文字を使う人間が必ずしもニコニコしていないという現実を考えるだけでも、ビジュアル・コミュニケーションの基盤の危うさが垣間見える。
●ビジュアル・コミュニケーションが発達すればするほど、他人を信頼することは難しくなり、人間関係がより希薄化する側面があることは否めない。