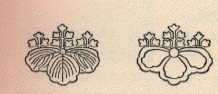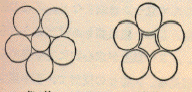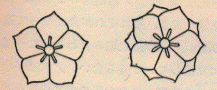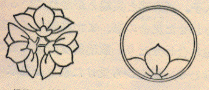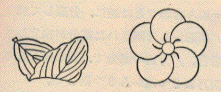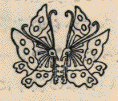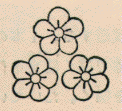1.現代に生きている紋章
シンボルとマークの役割とデザイン。
●時代と共に移り変るデザイン
・(ex)貴族や武家の時代に貴重だったシンボル
↓
・現在---交通標識などの社会的「権威」も与えられていない。
※シンボル…時代の要求によって、生まれてくるもの。
●デザイン→シンボル→紋章
・広告(屋外広告、新聞広告、TV CM)などからイロイロな広告から思い掛けない紋章を目にする。
・印象強いもの
(ex)<三菱鉛筆>---トレードマーク=<寄せ三菱>---かなり古くから。
<住友>---------トレードマーク=<井筒>
●マーク…消費時代なので、人々が多くの商品を企業の中から選び出す時に、視覚上のめどを与える重要な役割をしている。
●過去→現代へ。
・日本の古くからの紋章→現代にも生き続けている。
・装飾デザインとしても、本質的な強さを持っている。
・使い方や演出の工夫などによって、今日的な効果が求められる。
紋章とは---様々な社会を結び付ける共通の役割に適合したイメージへの改革や再創造によって、時代の要求に応じる。
●企業のトレードマーク
・企業や商業などの一種のトレードマークとして紋章が歴史上に登場した。
貴族や武家の専用物⇒町人、新興商人
(現実的な経済生活に自信と力を示し出した頃から〜)
・以前---経済生活などに力を出せなかった頃…。
大名、旗本、武士達の公務上、社会上にシンボルマークは、存在。
(ex)参勤交代
・江戸幕府で、参勤交代の時に、下座見(げざみ)役を大手門において、次に登場する諸大名の人数などをその紋章によって調べた。
(ex)鎌倉時代〜戦国時代
・武将や武士達---旗や幟(のぼり)に掲げた大ぶりの紋をゆったりとした衣服にすえていた。
(ex)江戸時代
・紋---四角四面の裃の定められた紋所に、小さく納まってしまう。
(幕府が諸大名を牽制したため。⇒紋章のデザインまでに及んだ。)
●紋章のパターン
・多様化してきた。
・江戸時代→町人文化の下からの盛り上がり
⇒紋章を装飾的にも実務的にも発展させた。
・職人、町火消しなど〜。
(一般庶民の好みを反映した芸人の紋章が多い。)
(紋章のサイズは、大きかったり、小さかったり様々である。)
(図形の変化にバイタルなものがみえる。)
・社会生活の意匠---屋号を決めた。また、のれんを工夫。
商業のパッケージや取り引き上の記号などに、古い紋章を新時代のシンボルに転化、変化を加えた。⇒再生していった。
●分類・構成・造形的な分類〜
・日本の文様---日本の文様は、日本独特な物もあるが、色々な渡来した文化に影響された所もある。
(ペルシア、東ローマ、インド、中国など。。。。。)
※視覚による歴史の、具体的な奇跡を残す文様の流れの中で、さらに注目
すべき系列として発達してきたのが紋章。
・公的な装飾から⇒個々の家系や家名のシンボル・デザインになっていった。
個の自覚と表現
・⇒文様に残された大陸や西方の影響を脱して、自らの造形言語を獲得する。
・日本の紋章---草木、華の紋章が多い。(独特の味わい)
・ヨーロッパ、中国の紋章---動物や人物を扱った紋章 ⇒日本の紋章と比べると多い。
<日本の紋章のモチーフ>
・自然現象、植物、動物、器具、建造物、幾何文様、文字、図符(源氏香などの図 形、呪符など。)
・構成や変形も独特な技法が使われている。
付加 …ある紋章に外郭の輪や角をつけたり、剣やつるなどを加える。
改造…紋章の主体を改造する。1本の線で描くのを陽紋→複線で描く陰文(かげもん)を作る。
・花の紋章などで、→裏を描く。蕚(がく)を見せている。
(裏梅鉢、裏菊等と、呼ぶ。)
・一重の花の紋を八重にする。
(葉のギザギザを鋭くして、鬼蔦、鬼桐等と、鬼をつけて呼ぶ。)
(尾形光琳の筆法にならった、光琳梅・光琳桐等。)
・正面からみた梅の平面図を向梅、横からのを横見梅、輪郭の内に覗かせた 形を取ったのが、覗き梅。
(上り藤丸・下り藤丸など。)
(方形を水平に置いた平目結。→(ひらめゆい))
(方形を45度回して、立てた角立目結。)
(平行四辺形の寄せかせ目結などの変化もある。)
・折って折り柏。・捻って捻り梅。・結んで結び雁など。
(他の紋章に見立てる。→別の紋章を作る擬態。)
→→→→桐の形をした澤瀉(おもだか)----澤瀉桐。
→→→→蝶の形をまねた桔梗(ききょう)----桔梗蝶。
合成---同じ紋章を2つ、または、2つ以上組み合わせる。
・対(むかい)蝶のように対(つい)にする。
(一対が抱き合っている。→ex:抱き茗荷(みょうが))
・違鷹羽(ちがいたかのは)のように長い紋を交叉する。
(同じ紋章の重なる重扇→ものを皿に盛り上げたような形の三盛梅。)
・3つ以上が求心的に寄せ集められた形。
(三寄(みつよせ)横見梅)
・寄せの反対で、引き離された姿。→離巴(はなれともえ)
・追銀杏(おいぎんなん)のように、尖端と末尾とを順に置き、それぞれが 丸くなって追いかけている形。
・2つ以上の組み合わさった一部分がお互いに共通している持ち合い。
・大形が小形を包んだ子持ちの形。→また、大形の中に、小形を重ねて入れる入子(いりこ)
・尖端と尖端とが、触れている頭合(かしらあわせ)
・末尾であわせた尻合(しりあわせ)
※結婚などで、双方の家紋を組み合わせたりする。
※政治的な配慮による追加や組み合わせもある。
※君主から受けた紋章を自家の紋章に組み合わせたりする複紋がある。
分割…組み合わせとは、逆。
分割して成り立つ紋章。
・原形から分割された部分が独立して用いられる場合。
(分割の部分で、別の形を作る、割紋。(わりもん)割方は、2つ割から8割まで。)
省略…紋章の一部を省略する。
(EX.三星一文字の一文字が略され三星だけになったり、桐の葉脈が略されて筋無桐(すじなしきり)にある場合。)
※多様性---及ぶ限りの意匠を試みて来た日本人の、なみなみならぬ、感性と技術の高さが表れている。
●紋章の形と変化を表す用語が多い。
●古い言い回しや言葉の使用が多い。
<<現代のグラフィックデザイン>>
●印刷、出版、編集の仕事でも、昔からの日本の用語なしでは、すまされない場合もある。
●紋章…名称、用語も歴史を考えて理解すれば興味の涌く言葉が多い。
<<紋章と視覚伝達>>
・紋章---視覚経験に、もっとも基本的な丸と角の世界である。
シンメトリーが、求められる。
●その安定し、完結した感じの形は、多くの人に好まれる。
●紋章=一つの確立された世界である。
(それだけに、新しく取り上げた、トレード・マークとして再創造する場合に、丸や角で囲むと目立たなくなる事もある。)
→→→→丸や角の、おびただしい基本形に紛れ込んでしまう。
●囲みのない紋章の原形自体が、強い造形の言葉を示している時は、単独に扱って効果を上げる。
※しかし→同じ大きさの原形を輪で囲むと、囲まれた原形が大きく見えるという効果もある。
※幾何学的錯覚---紋章には充分生かされている。
※理論とは別に意匠の創造果たされるもの。