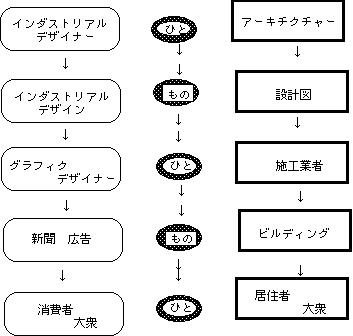
§4.伝達表現
●伝達…ある命令、質問、希望の表現は、誰かがその命令、質問ないし、希望に相当する印象を受け取るまでは、まだ、受け取らない限り、伝達されない。
それに相当した印象が受け取られたかどうかは、返される伝達内容をみればわかる。
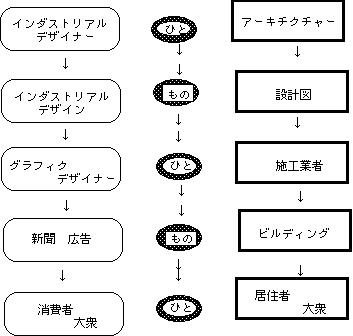
●意志を的確に伝えたい⇒ものにスバリ、イメージを注ぎ込みたい。
そのものに秘められた意味をはっきりくみ取らせるようにする。
◆言語伝達…人から人へと伝達されるものを通さない。デザインに見られる視覚伝達は、人からもの、ものから人へ伝達されて行くようである。
◆視覚伝達…客観的事実を伝達する事かななりたつ。
視覚伝達→→→広告伝達、公告伝達、プロダクト伝達、生活環境の伝達などがある。
<伝達というもの。。。。>
●伝達…ものを媒介として人と人とが結ばれる事を意味する。
4つの形式がある。
・マーケティング・コミュニケーション→ビジュアルデザイン、その他のビジュアルデザイン、プロダクトデザインの伝達性、生活環境それ自体の持つ伝達性。
※↑これらは、言葉では伝達出来にくいある種のイメージを伝える事に便となる。
●もの(デザイン)による伝達、わかりやすい(説得力を持ち)、第一印象もよい (印象力のある)事が必要。
●説得力と印象力とを伝達機能と考えて、伝達性に重点をおく。
※表現的性質・表現的性質は芸術家の伝達手段である。それは、芸術家の注意をひく。それを通して、芸術家は自分の体験を理解したり、解釈したりする。それは、芸術家が創造する形式形態を決定する。それゆえ、芸術学生の訓練は、根本的にこれらの性質について感覚を鋭くし、鉛筆、筆、ノミのひとつ、ひとつ、の使い方に至まで、表現を指導理念としてあおぐことである。 L.アルンハイム 『芸術と視覚』
<伝達と表現の関係>
●「伝達」の言葉の中に、本来「表現」という概念も含まれている。
しかし、伝達がすなわち、表現ではあり得ない。
・「伝達」---「あるがままを伝える」「事実を伝える」「真実、真意を伝える」
→→→→→→→事実の真意は、説得力を持ち、印象力のあるものでなければ、伝達される側を納得させる事が出来ない。
・「ありのままを伝えたり、事実を伝える」必要は更にない。
・あるがままよりも、それをある程度演出し、そこに作家の内的必然性を注ぎ込み、その過程で出来上がった一つのイメージ(実感)それ、自体を伝える。
・「表現」---表現における実感とは→芸術にあっては、いのちの感覚といわれるもの。生のリアリティそのものにほかならない。
・「人がここに生きる」という生存の事実の証として、表現は一つの実感を伝える。
・デザインにあっては→一つの実感は暮らしの実感。
・暮らしの実感…「生活とはいかにあるべきか」との生活の今日的なあり方を裏付ける理念にほかならない。
表現記号がいのちの感覚を訴えるのに対して→→→
スライグ・リンドベルズのデザインやロング・ハウスの稚拙なデザインは、暮らしの感覚をしみじみと感じさせずにはいない。こうした、両感覚がよいデザインの条件である。
※表現←→伝達---なかなか明確に区別出来ないが、実感の伝達と事実の伝達とのその伝え方の程度によりこれを区別するより他にすべ
がないのではないだろうか。
<イメージ>
●イメージ●
・イメージとは、人が事物について懐く既成概念としての映像である。
しかも、それは、単に、映像だけではない。
その映像を中心として、それに印象や感じや考え方が結び付けられた、『ひとかたまり』をいうのである。
戸川行男「モチベーション,リサーチ」
・イメージ…この言葉くらい曖昧に使われている言葉はないだろうと思う。
物自体、デザインそれ自体ではない。
人がもの(デザイン)に抱く、印象であり、人がデザインを創る時に心に描く、一つの心像にほかならない。
・イメージ⇒デザイン…デザイン自体に対して、創る側もこれを受け入れる側も共に抱くもの。
そのかぎりにおいて、デザイン(もの)を離れてはなりたたない、デザインに伴う一つの実感である。
・デザインを受け入れる側…かならずしも、人が共通した実感を持つ訳ではない。
個々人の生活の実状に即して、その実感はかなり異なってくる。
・だか、そこには、まずそれを創った人の実感がズバリ反映されていなければならない。
・万人に対し、なんらかの共通の実感を与えないようでは、大衆の生活には役立たない。
※一つのイメージは、人からデザインへ、デザインから人へと再び伝えられて行く。
もともと、「ひと⇒もの⇒ひと⇒もの⇒ひと」という系列を媒体として、イメージ伝達されるものに他ならない。
・統一あるくらしのイメージの一貫された伝達にこそ、
「デザインが大衆の時代に咲く花」
<アイディア>
●V.ファンジェ『創造性の開発』
※「アイディアの発見に努力する場合には、いつも考え付くたびに、記録する事が極めて大切である。」「しかも、一旦、アイディアのリストがまとまったら、一枚の紙の縦横左右にアイディアを書きとめて、その潜在能力を倍加させる事ができる。」「アイディアを他のアイディアと残らず組み合わせる事によって、更に多くのアイディアを作り出す事が出来るのである。」
(例)→→ル・コルビジェのロンシャン教会
⇒アイディアが修道女の帽子にあった。
(例)→→丹下健一 香川県庁舎
⇒日本の古代建築の中に、その発想の源が求められるというアイディアの良さ。
・あらゆるデザインには、それが具体的にイメージニングされるための一つの切っ掛けがある。
◯この発想⇒アイディア、切っ掛けを生む源⇒アイディア・ソース。
●アイディア…「くらしのイメージをどう実現すれば良いのか」
・↑それに応じるべき一つの構想に他ならない。
・「一つのイメージをどう伝達すべきか」
・↑それを進める為の、着想、手段で、ある。
●着想や構想…アイディアを作り上げる為の具体的な方法を思い付く事を言う。
●解決方法…創る人の心に描かれている一つのイメージを的確に具体化しうるための解決方法。
→一つあって、二つなはない。この一つあって、二つない解決方法を思い付く事こそ、真の意味で、「よいアイディア」である。
・人間工学の成果…デザインにとって、一つのアイディア・ソースとなるだろう。
・クリエイティブなアイディア
(例)亀倉雄策 オリンピックマーク
・五輪と日の丸に見られる円形記号に一つの共通性を見い出す所に、アイディアがあった。
(例)クリスチャン・ディオール
・ディオールのファッションデザインの十字のシンボル
→十字のシンボル…人体それ自体の直立して手を左右に広げた有り様を表現している。