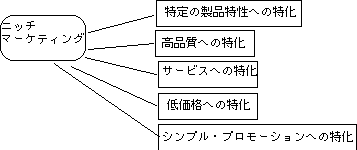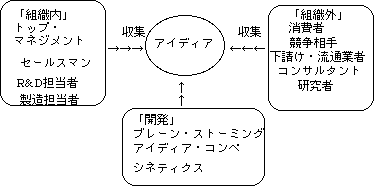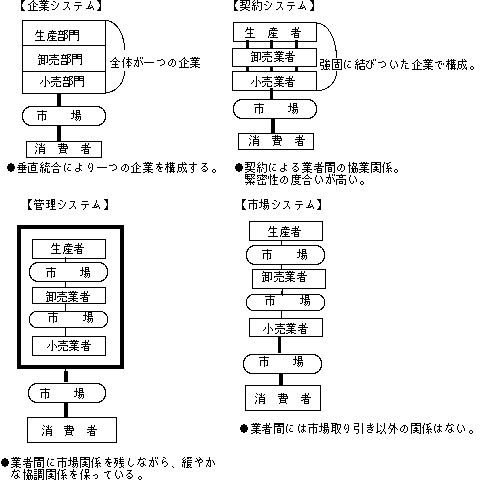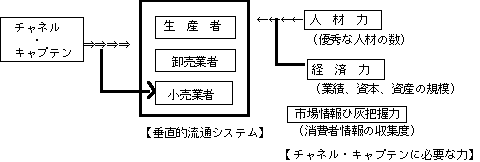16.ニッチ・マーケティング
◆市場の適地やすき間を見つける。
市場には、大手の企業が見逃した「適地」や「すき間」がある。
これを中小企業が見つけ、小回りの良さと専門性を発揮して、効率的に収益を上げていく計画的な活動をニッチ・マーケティングという。
ニッチ(niche)とは---これまでに他の企業によって手をつけられない潜在性
のある市場。
※メリット---これを発見できれば、販売数量および販売額の面で高い成果が得られる。
→成功の評判を聞いて競合企業が入ってくるまでは、独占市場を享受することができる。
<<ニッチ・マーケティングを実施するには>>
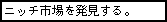 (ニッチ市場を発見するためには、かなり詳細な市場細分化を行う。)
(ニッチ市場を発見するためには、かなり詳細な市場細分化を行う。)
↓
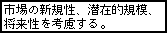 →
→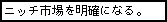
{企業}新規のターゲットとして選別した市場
製品、価格、チャネル、プロモーションなどの面で先鋭化→専門特化したマーケティングを実施。
ニッチ・マーケティング---市場の新発揮できるセグメントを探し、それを徹底的に追求していくもの。
<<ニッチ・マーケティングによる専門特化の方向>>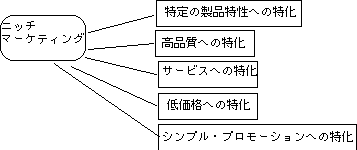
↓
●シンプル・プロモーションとは、プロモーションコストをかけないマーケティングのこと。
●詳細な市場細分化により、ニッチ・マーケティングを発見した後、そのマーケット・ニーズを満たすような多様な専門特化が模索される。
1.製品を考える
◆製品を構成する要素
消費者が製品を買う場合には、単にその物理的な構造物だけを求めているわけではない。
製品の基本機能が果たす効用やっとベネヒットのみならず、ブランドやスタイルなどが醸し出すイメージを求めている。
<<製品の要素>>
1.基本機能{エンジン}
消費者のニーズを満たしてくれる、製品による必要低限のはたらきのこと。
(例)
自動車→エンジンを動かしてある地点から別の地点へ移動ができる。
あるいは、物を運べるという働き。
2.物的特性{素材成分、耐用年数、危険度、サイズ、重量}
基本機能を支える製品の物理的な性質。
製品が何から出来ているか(素材成分)、どれくらいの期間使用が可能か(耐用年数)、どのくらいの大きさか(サイズ)
など客観的、計量的に把握することのできる製品の性質。
3.イメージ特性
{メーカー名、スタイル、ブランド、色彩、装飾、包装、オプション}
製品の物理的な機能にはさほど関係ない。
メーカー名、ブランド、スタイルなど製品のイメージを形成する上で非常に大きな影響を及ぼすもの。
→主に、マーケティングに発揮される部分。
4.付加的サービス特性
{保証、点検・修理(メインテナンス)、クレーム処理、配送、据え付け、支払い条件など。}
保証、点検、修理、クレーム処理などのアフターサービスや迅速な配送など、製品に追加されると信頼性が一層増す。販売量の向上にも大きく影響する特性。
↓イメージ特性、付加的サービス特性(製品)自動車 
●最寄品→単価が安く多頻度に購買され、居住地から近い店舗で購入される製品。
食料品や日用雑貨が典型。
「最寄品」---習慣的購買・近隣店舗での購買・相対的に低価格・高い購入頻度・高い製品の事前知識
●買回品→品質、価格について比較を行う製品で、多様な品揃えをしている店舗が利用される。
衣料品が典型。
「買回品」---比較購買・商業集積地での購買・相対的に中価格・低い購入頻度・低い製品の事前知識
●専門品→価格の高低や店舗の遠さなどに関わらず、消費者が特別の執着を持った製品。
美術品、高級車が典型。
「専門品」---ブランド指名買い・特定店舗での購買・相対的に高価格・低い購入頻度・高い製品の事前知識
3.新製品開発のプロセス
◆新製品ができあがるまで
組織が存続・発展するには、常に魅力ある新製品を開発するための努力が必要。
新製品を開発するには、たくさんのアイディアを出し、それを市場性、製造可能性、経済性などの観点から絞り込んでいく。
<<新製品のプロセス>>
1.アイディア収集と開発
組織内、組織外からアイディアを収集して、同時にブレーン・ストーミング(活発に意見を出し合うためのルールに基づいた会議)などで、積極的にアイディアの開発を行う。
↓
2.スクリーニング
チェックリストなどを使って、組織の方向性、市場性、製造可能性などの観点からアイディアの絞り込む段階。
↓
3.経済性の評価
残った有望なアイディアをより具体的なコンセプトに変え、それがどの程度の経済性を生む可能性があるかを評価し、さらに選別が行われる。
↓
4.開発
抽象的なコンセプトを実際の製品のプロトタイプ(ひな形)に具体化する段階。
↓
5.マーケット・テスト
広範囲の市場に販売して失敗すると大きな被害を受ける。その前に、限られた市場で試験的に販売してみる段階。
↓
6.市場導入
今までのステップをクリアしてきたものを、新製品としてタイミングを計りながら市場化する段階。
<<アイディア>>
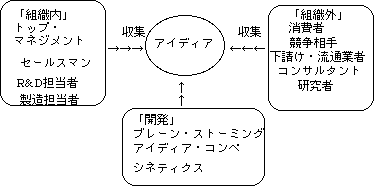
4.製品ライフサイクル
製品にも、誕生から〜死滅までの一生がある。→ライフサイクル
*売り上げ高の水準や競争状態の違いに基づいて、考えられた。
1.導入期→2.成長期→→3.成熟期→→→→→4.衰退期(人気殺到)(ニューモデル投入)(撤退)
の、4段階に分けられる。
1.垂直的流通システム
◆生産者と流通業者の協調
『製品の流通は、独立した業者による市場取り引きよりも、縦のシステムを作った方が良い場合がある。システム全体の合理性という観念から作られた、縦の協調関係による企業組織を垂直的流通システムという。』
<<垂直的流通システムと市場システム>>
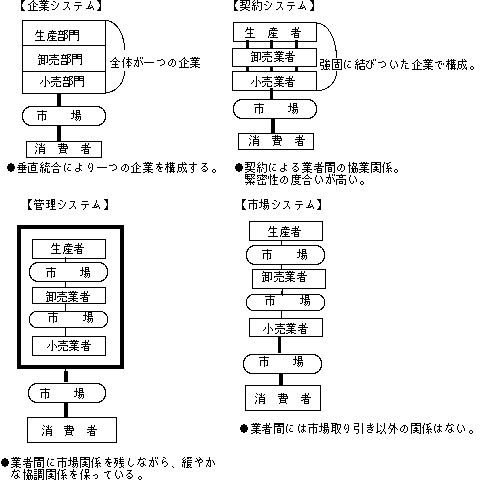
1.企業システム
垂直統合。
(例)生産者が流通業者を「所有」することによって、卸売業者や小売業者を自己の傘下におさめてしまう。
各業者間での市場的な取り引きは完全になくなり、それぞれが一つの企業の生産部門、卸売部門、小売部門として機能することになる。
2.契約システム
チェーン店契約のように、法律的にも形式的にもしっかりとした「契約書」を交わすことによって、業者間での垂直的な協業関係を築くもの。
企業システムと異なり、「所有」されていないので、個々の業者にある程度の自主性が認められる。
3.管理システム
「所有」や「契約」という形での業者間の拘束はなく、緩やかな協調・協力関係を持ったシステム。
リーダー企業によってシステム全体の方向づけはなされるが、業者間には市場取り引きも残り、各業者の自主性の範囲の最も広いシステム。
2.流通系列化
◆メーカーの流通コントロール
『メーカーが自社の製品を取り扱う流通業者から販売上の協力を得るために、さまざまな強制をしたり、援助をしたりして、組織化を促し、流通経路全体をコントロールする行為を流通系列化という。』
◇競争の過熱化している現状をふまえて、競争の単位は個々のメーカーというレベルだけでなく、卸売業者や小売業者を巻き込んだ
『チャネル・システム』という単位に変わってきている。
◇メーカーは、流通業者を自己の手足のように考えて、1つの組織のように緊密しな相互関係を保ちながら、コントロールする。
<<経済社会にとってのメリット>>
1.流通業者の統合・整理による流通の合理化
2.業者間相互の関係緊密化による消費者情報伝達の効率化
3.アフターサービス体制の充実。
<<デメリット>>
1.価格競争の制限。
2.流通業者の自主性などの喪失。
3.新規参入の阻害など。
3.チャネル・キャプテン
◆垂直的流通システムのリーダー企業
『競争優位性を確保するために生産者と流通業者が協調関係を持つ垂直的流通システムを形成することがある。
このシステムを全体にとって望ましい方向へ導くリーダー企業のことをチャネル・キャプテンという。』
<<垂直的流通システムにおけるチャネル・キャプテン>>
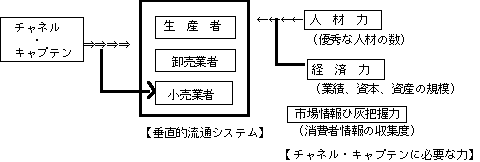
●システムを運営するリーダー企業は、トータルのパワーの最も高いところである。
●人材力と経済力は生産者が高く、市場情報把握力は小売業者が高い。
一般のシステムでは、このどっちかがリーダーとなる。
4.バイイング・パワー
◆巨大小売業者による地位の濫用
『大型小売業者は、消費者に多くのメリットを提供してくれる。しかし、製品の納入業者に無理を強いることがある。これが、バイイング・パワーである。』
◇百貨店、総合スーパーなどのGMS(ジェネラル・マーチャンダイズ・ストア)、門量販店などの巨大小売業は、一度に大量の製品を購入する。
→だから、製品の納入業者にとっては、これらの小売業が得意先になる。
◇大量に製品を販売してくれるという単に経済的な問題だけではなく、百貨店のなのに、伝統の「のれん」があったり、全校チェーンのの総合スーパーのように「全国的知名度」が高かったりという付加価値もある。
◇納入業者にとっては、信頼できる立派な小売業者と取り引きできるという
ステータスとしての価値がある。
<<バイイング・パワーの問題>>
◇メリットを背景に大型小売業者がメーカーや卸などの納入業者に不利益な条件の取り引きを強制したり、取り引きに関係のない行為を強要したりすることが、バイイング・パワーである。
(例)不当な値引きの要請、映画のチケット、美術品などの押し付け販売、協賛金の要求など。
※優越した立場を利用してさまざまな行為が行われているが、「優越的地位の濫用」として、独占禁止法によって規制されている。
5.チェーン小売業
◆水平組織を構成する小売業
『小売業は、規模の利益を得るために、水平的な組織を作ることがある。これを、チェーンという。
経営の主体や方式によって、レギュラー・チェーン、ボランタリ−・チェーン、フランチャイズ・チェーンに分類できる。』
1.レギュラー・チェーン(コーポレート・チェーン)
●個々の店鋪は、すべて直営店で同一企業に属している。
●本部のコントロールは絶対で、基本的に店鋪の行動の自由はない。
2.ボランタリ−・チェーン
●個々の店鋪が独立した企業である。
●本部のコントロールは、さほど強くなく、主に共同仕入れや共同販売を行う協業組織である。
※小売業のボランタリー・チェーンのことを特にコーペラティブ・チェーンということがある。
3.フランチャイズ・チェーン
●フランチャイズ契約によって構成された組織で、本部をフランチャイザ−といい、加盟店をフランチャイジーという。
●製品やサービスの仕方に本部からのコントロールを受ける。
※本部からのコントロールを受けて、加盟店の行動は制限されるが、レギュラー・チェーンほどではない。