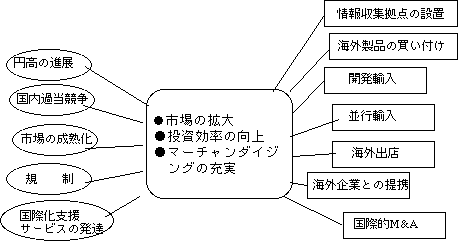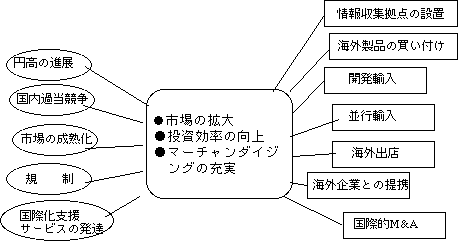
14.エリア・マーケティング
◆地域特性を考える。
1980年代~重視されるようになった。
エリア・マーケティングとは…
ニーズは地域によって違う場合がある。
組織が広い範囲を対象市場にするには、地域の特性に合わせたマーケティングが必要になる。
※『標準化マーケティング』
地域の異質性を意識しないで、どの地域へも同じマーケティング・ミックスの情報で取り組むもの。
◎エリア・マーケティングは、マーケット・セグメンテーションの地理基準はとくに重点をおいて対象市場を絞り込むもの。
◎地域の特性を徹底的に分析して、限定されたニーズにきめ細かく応える。
(例)
・加工品で同じブランドを付けながら、
関東地方---濃い味。関西地方---薄味。
塩の味をコントロールすることがある。
・エリアのローカル製品として~
地域限定のビール、ジュースなど。
※その他
デパート、百貨店で外商部門のひいきが伝統的に多い地域の店舗では、それ以外の店舗より外商部門の販売員を多く配慮しておくそうだ。
15.グローバル・マーケティング
◆全地球的規模で事業を展開
「地球全体を1つのマーケットとしてとらえる。」
○グローバル・マーケティング
国境というボーダーにとらわれることなく、全地球的規模で資源や市場機会を捉えるマーケティング。
世界のベスト・ソースを常に追求するマーケティング。
1.資源---価格や品質、納入ルートなどを総合的に評価した場合に最も有利な国から購入する。
2.生産---労働の質とコスト。生産設備などを考えて最も生産性の高い国で製品を作る。
3.販売---所得や消費性向などの面で最も販売成果の上がる国で製品を市場化する。
※本国、外国とかいう概念を取り払って=ボーダーレス、地球全体を1つのグランド・マーケットとして実行される。
(例)イーストマン、コダック、コカ・コーラ、P&Gなどが、グローバル・マーケティングを実践する企業。
日本の自動車、電機、精密機器などのメーカーもほぼ同じようなマーケティングが実行されている。
流通業---以前から総合商社がグローバル・マーケティングを行っている。
近年、小売業でも売場面積が国内よりも海外の方が広いヤオハンに代表されるように、単なる日本人向けのお土産屋ではなく、地元住民の購買生活に根づいた本格的な事業展開をするところが出てきている。