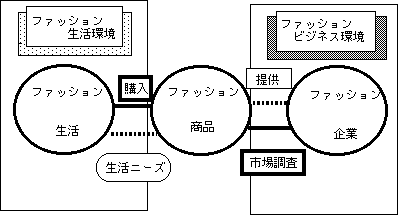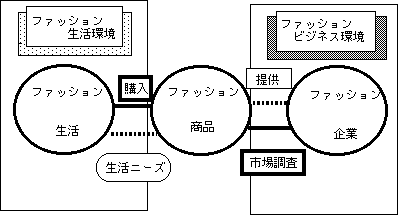
§1.ファッションとファッション・ビジネス
1.<<定義と概念>>
●ファッション…一言で言うのならば、『流行』
→この場合に、あらゆる事物、あらゆる事象にみられる様式(スタイル)の「変化」 が前提である。
●変化して行く様式…その変化した様式を多くの人々が「受容」するという条件が必要。
●問題点…様式の変化と受容がその時代の社会構造や経済構造、更に産業構造や教育機関を包括する社会構造と相関性を持つという事。
◎定義1◎
・風俗の枠の中で、部分的、一時的に新しい傾向が生まれ、それが社会のある部分の人々の間に広がる時、これを流行と呼ぶ。
(参考資料:⇒南博:『社会心理照魔鏡』)
◎定義2◎
・流行は、創出者、伝播者、追随者という、3つの要素の上にメカニズムが存在している。
(参考資料:⇒佐藤智雄:『流行-その魅力分析』)
◎定義3◎
・ある一定の時代に、広汎に行き渡るスタイルで、共通の知的活動であって、同一の刺激に対して、同一の方法で反応するという条件が必要である。
(参考資料:⇒P.H.Nystorm:『Economics of Fashoion』)
◎定義4◎
・人間の熱狂的反応が価値付加過程を経て、顕在化する一つの側面が流行である。
(参考資料:⇒N.J.Smelser:『Collective Behavior』)
●定義のまとめ
・流行とは…。
・事物・事象の様式の変化という前提をふまえて成立する社会現象であり、この様式 の「つくり手」があり、その「送り手」があり、それによって創出される事物・事 象環境に、人々が自己同一化(アイデンティティ)を行う事で成立する。
・多くの消費という行動で、その新しい事物との自己同一化を行う過程は、時代性を も含めた、いわゆる社会構造とのかかわりでとらえる必要がある。
2.<<社会構造との関係>>
・新しい様式に対する願望…人間の歴史の成立とともにあったもの。
・国家の体制に関わらず、共有されるもの。
→→→日本の封建制度にみられたように支配者層のみがその願望を達成した時代があり、庶民はむしろ、禁令、触書、口上などによって達成が不可能であった時代がある。
⇒⇒⇒これは、明治を中心とする近代化社会の到来によって、洋風化の受容が国家的急務となるにつれて、また、富国強兵や殖産興業という国家的政策を通じて徐々に庶民の側へも浸透し始める。
→→→大正期を通じて、庶民の側に新しい様式受容のリーダーが出現して、これをきっかけに庶民の流行追随が進行したと考えられる。
・結論---新しい様式への自己同一化は、社会の仕組みと関わり合いがあるという事。
・(現代の社会構造)
・資本主義社会であり、何よりも利潤の追求を目的とする、いわゆる企業支配の社会 といえる。
そして、一方に、消費行動による利潤の追求もあるわけである。
・生産、流通、消費のためのシステムによって構築されているのが現代社会であり、大衆社会そのものである。
・従って、大量生産、大量販売、大量消費の関連図を土台に、流通及び、宣伝の交錯 のもとで、現代人は同一化を衣、食、住、の分野で選択しているといえる。
・1つの様式が創出され、市場性を持つと、次の新しい様式の創出がなされる。
→それぞれの分野、衣、食、住、における、ものの創出があり、それらを情報とした大衆の側で、それを消費しようとする行動をおこす。
・結論---新しい様式の受容があって成立する社会現象や社会事象がファッションということになる。
3.<<衣服の社会性>>
・既成概念:ファッション=衣服の流行
・生活事象をとらえるのに、衣・食・住というように、人間にとって、衣服は、感心事の第一条件である。
・歴史
→封建社会において〜
・支配階級と被支配階級との間に厳然とした衣服着用の区別があった点でも明らか。
・金銭的文化の表示としての衣服というとらえ方をしている点にもみられる。
→近代社会において〜
・西欧化の受容度は、鹿鳴館に典型があるように洋装によって表現された。
・官職関係の制服、学生服は、職種や帰属を明らかにしたもの。
・1941年に始まる太平洋戦争は、国民服の制定も、それを着る事により、国を挙げての戦争に参加しているという事を表明したわけである。
→職人社会では〜
・印半纏(しるしばんてん)や法被(はっぴ)が職能を表現して、江戸時代の火消し装束も、雅楽や能の装束も、すべて役割や地位を表明するのもであった。
・この他---学生服、職能服、特殊服、ユニフォームなども、同じような事言える。
※衣服は、それ自体は、単に縫われたものに過ぎないが、それが着られる事によって 「社会的機能」を持つと言う事。
→現代社会において〜
・服種そのものが、化・合繊の開発によって、豊富になった事も手伝って、日常生活面では、厳然とした衣服の「直感的承認性」は、見受けられない。
・しかし-----社交面→フォーマルという価値観が支配的になり始めている事 は看過できない。
⇒このような事は、衣服が直感性承認性という性格よりもいわゆる、「非言語コミュニケーション・メディア」としての機能を重視されはじめたと、言う事にもなる。
※着衣は、そのまま、他者とのコミュニケーションをしているということなのである。
(ex)『選挙の時に、それぞれの政党の政策を色や標語に明示するよりも、候補者は、もとより、運動員に至までユニフォームの着用が目立っている。』
⇒衣服が非言語コミュニケーションのメディアであることの表象である。
・トレーナーなどの着用が日常化している事への自己同一化の表象ということ。
4.<<衣服の流行について>>
●『流行』→あらゆる事物の様式の受容が、集団的な地域的な、国家的なあるいは、世代別、性別的な規模で行われた場合の社会現象を言う事が、ほぼ明白になっている。
●『衣服』→直感的承認性という機能と、一方に時代性の自己同一化(アイデンティティ)という機能を具有する非言語(ノンバーバル)コミュニケーション・メディア。
●衣服の流行の構造分析
・素材…原料、染織、織りなどから様式創出に大きな影響を与えている。
更に、裁断、縫製工程、仕上げ工程も同じ。
(背景)→農業、林業、漁業が直接的、間接的に影響し、産業、工業、政治、経済の社会的施策までが関連してくる。
・材料…道具、機械、空間というような装置、環境、知識、技術というような情報環境、技術環境も不可欠の要因。
・他方→着装する人間側では、その人間の衣食住を規定する、いわゆるライフスタイルの問題が影響するわけである。
1.その人間の所属集団、地域社会というような生活構造的背景
2.因襲、風習、慣行、というような習俗的背景
3.習慣、作法、慣習というような伝統的背景。
4.規則、法というような規制的背景の合成から成り立つ文化構造的なもの。
※衣服は、1着の新しい様式のものを一見して衝動買いをするにせよ、その行動の背景には、その人間の「所属」や「帰属性」さらに、「文化度」というものが潜在的に影響して存在しているという事になる。
(変化した様式を受容する事によって成立する、社会現象。)
↓
(社会現象⇒社会構造とのかかわり合いによって生起する。)
●ファッション⇒
衣服…初源にあった、身体保護、装飾機能も然る事ながら、むしろ社会生活における非言語コミュニケーション(媒体=メディア)として機能を具有する。
●ファッションの動向…
衣服に関してよりも、衣服も他の食や住とを包括し、その上にレジャー、音楽、会話なども包括した、いわゆる「ライフ・カルチャー」の構成 要素というとらえ方になる。