詳しくは、写真をクリックしてください。
カトウミノルのホームページ2006
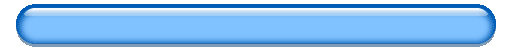
妙高生き物調査(昆虫類:トンボ)
 |
キトンボ 体長約42mm、後翅長約30mm。体全体が橙黄色で黒斑を欠く。老熟してもほとんど赤化しない。♂♀とも翅の先端は前縁部を除き透明、他は広く橙黄色をおびる。詳細はこちら |
| ショウジョウトンボ 典型的な水田のトンボで、夏に赤い色をしているトンボは本種である。西南日本では各地でごくふつうに見られるが、東北地方では産地が限定される稀な種である。開放的な水面を好み、水域が植物で覆われてくると見られなくなる。詳細こちら |
 |
 |
オオシオカラトンボ おもに平地から低山地の樹林が縁にある池沼や湿地、水田、緩やかな流れの溝川などに生息する。成虫はやや薄暗い小水域を好む性質が強く、明るく広々とした水域を好むシオカラトンボとは明確にすみ分けている。幼虫は、植物性沈積物の陰に潜んだり、柔らかい泥の中に浅く潜って生活している。 詳細はこちら |
| クロイトトンボ おもに平地や丘陵地の挺水植物が繁茂する池沼などに生息しているが、ハスの生えた公園の池など、人工的な水域でも見られる。幼虫は、水中の植物などにつかまって生活している。かつては、水生植物のまばらな小規模な池沼、水溜まりなどにも普通に見られたが、近年ではこのような水域でもあま り見られず、確認できても個体数は少ない。詳細はこちら |
 |
 |
アオイトトンボ 体長約40mm、後翅長約22mm。胸側の金属緑色は上端で後方にのびるが、第2側縫線にとどかないことが多い。♂は成熟すると金属緑色以外の部分が黒色みをくわえ、白粉でおおわれる。詳細はこちら |
| アキアカネ アキアカネは秋に見られる茜色のトンボの意味。一般的に「赤トンボ」の名前で親しまれている。東北ではトウガラシトンボ、カミナリトンボなどと呼ばれる。詳細はこちら |
 |
 |
ノシメトンボ おもに平地から低山地の、水際に植物が繁茂する水深の浅い開放的な池沼や水田などに生息する。幼虫は水底 の植物性沈積物の陰に潜んで生活している。周辺に林地を有する水田環境で普通に見られ、個体数も多い種であるが、地域的にはまったく見られない場所もある。 詳細はこちら |
| オオルリボシヤンマ 体長約80mm、後翅長約55mm。ルリボシヤンマに似るが、胸側の前方の淡色条の上端はまさかり形に後方で広がる。 詳細はこちら |
 |
 |
ギンヤンマのヤゴ おもに平地から低山地のやや大きい開放的な、挺水植物が繁茂する池沼を好む。水田や湿地の滞水などにも生息し、しばしば公園の池や社寺の境内池などでも見かける。 詳細はこちら |
| オニヤンマ 平地から山地の小川や湧水、湿地、滞水など極めて広範囲に渡って生息し、幼虫は水底の砂泥中や落葉など植物性沈積物の下に潜んで生活している。 詳細はこちら |
 |
 |
セスジイトトンボ おもに平地から低山地の挺水植物・浮葉植物・沈水植物が繁茂した池沼や、湿地の滞水、浅い止水や緩い細流などに発生し、山間の水田に多い。長野県では白樺湖(1,420m)のような標高の高いところでも観察されている。 詳細はこちら |
| マユタテアカネ おもに平地から低山地の、挺水植物が繁茂する池沼や湿地、湿原、水田、溝川などの止水域に生息する。林縁の木 陰やうっぺいした場所など、やや薄暗い環境を好む傾向がある。幼虫は水底の植物性沈積物の陰や柔らかい泥の上にうずくまっている生活している。 詳細はこちら |
 |
 |
ハグロトンボ おもに平地から低山地のヨシやミクリなどの挺水植物や、エビモ、バイカモ、セキショウモなどの沈水植物が繁茂する緩やかな流れに生息する。幼虫は水生植物の繁みの中で植物につかまって生活している。 詳細はこちら |
| モノサシトンボ 体長約42mm、後翅長約25mm。♂の地色は黄緑色で、腹部第3〜7節の基部が淡色で、いわゆるものさし状となる。 詳細はこちら |
 |
 |
コオニヤンマ 山地渓流から低山地の川の中流域に発生し、成虫は流域の周辺の小枝や石の上などに静止していることが多い。 詳細はこちら |
| ハラビロトンボ おもに平地や丘陵地の挺水植物がよく繁茂した池沼や湿原、腐植栄養型の沼沢地や湿地などの浅い水域に生息する。幼虫は挺水植物の根際や植物性沈積物の下、柔らかい泥の中などに潜む。 詳細はこちら |
 |
 トップページへもどる
トップページへもどる