長野県_阿智村の植物(木本)
更新日(2020/07/03) 新着写真⇒
風景のページ 2013/06/25 の正解はこちら
★ 何気ない自然
● 何気ない自然に興味のある方は ノリウツギと○○ をご覧ください
- 木(木本)の写真を撮るのは、私にとっては難しい作業で、大きくならない木を撮りたがる傾向。
- 今後はアプローチの仕方を工夫する必要あり!
- 写真を載せることに時間を取られましたが、少しづつ記述も増やしていきます。
★ 気になる植物(木本) ベスト5 ★
● ↓ 気になる木なのですが ...まだ何物か調べておりません ↓


- ※「阿智村の植物 レッドデータブック」では、"ミヤマヤナギ" は"絶滅種" になっていたと記憶しておりますが (間違っていたら御免なさい)、微妙な場所で生きています。
- ※ "ミヤマザクラ"、"イヌザクラ" も確か "絶滅種" になっていたと思います。ミヤマザクラは1400mくらいのところにありますし、イヌザクラも、2018年に古木ですが "ある沢" で見つけました。
★ お薦め木本 ★
- 1.エドヒガン 2.マメザクラ 3.タカネザクラ 4.ミヤマチョウジザクラ 5.ヤマザクラ
6.オオヤマザクラ 7.カスミザクラ 8.ミヤマザクラ
- ※ 日本の野性の桜(サクラ属/サクラ亜属)は、10種類しかないそうです。 そのうち、オオシマザクラは伊豆半島と伊豆諸島、クマノザクラは紀伊半島でしか見られない地域限定種だそうです。 つまり、この2種を除くと日本の野生の桜は8種類です。
- ※ "ずく散歩" のフィールドでは、なんと日本の野性の桜、8種類を見ることが出来ます。 (多分、間違っていないと思いますが) これは、チョット自慢です。
2020年7月
2020/07/02
* バイカツツジ
* バイカツツジ20_1 2020/07/02 標高1150m ルートI.


* ヤマアジサイ 標高1000m ルートA. * コアジサイ 標高1150m ルートI.


2020年6月
2020/06/09
ナワシロイチゴ(バラ科/キイチゴ属) / 付録_エビガライチゴ
- これがナワシロイチゴの開花した花です(萼片は開くが、赤紫の花弁を開かない)
- 私のお気に入りのエビガライチゴも花の色は白いが同じように花弁を開かない花を付けます。
※ 2か所で確認していたのですが草刈りの被害にあって何年かは見れそうにありません - 2020/06/09 標高1000m ナワシロイチゴ(バラ科/キイチゴ属)
- 2018/06/19 標高1150m 付録_エビガライチゴ(バラ科/キイチゴ属)



コゴメウツギ(バラ科/コゴメウツギ属)
- 地味な植物(木本)なのに何故か毎年、蕾と花の写真を撮りたくなります
- 2020/06/09 標高1100m コゴメウツギ(バラ科/コゴメウツギ属)

コゴメウツギ(バラ科/コゴメウツギ属)
コゴメウツギ(バラ科/コゴメウツギ属)
コゴメウツギ(バラ科/コゴメウツギ属)
ヤマツツジ
- 2020/06/09 標高1350m ヤマツツジ/ 今年は遅いがやっと満開のヤマツツジ



2020年5月
2020/05/28
ウラジロモミ
- 2020/05/28 ウラジロモミ(一本立の大きな木はウラジロモミです)



○○アオダモ
- このアオダモがある場所は、キノコに時間を取られるのでいつも見ているわけではありませんがこの日はやけに目立っていた
- アオダモの仲間であることは分かるが、種類を特定できるスキルを持ち合わせておりません
- 2020/05/28 標高1450m ○○アオダモ



2020/05/25
ミツバウツギ
- 変な花も色々とありますが、このミツバウツギの花も一度見ると忘れない
- 花弁のように見えるのは白い萼片、花弁は雄蕊と並行して直立し花弁には見えません(右下)
- 2020/05/25 標高1000m ミツバウツギ



コマユミ
- 2年前までは同じ場所にツリバナもあったのですが、伐採されていました
- 同じ場所にあった時は、簡単に比較ができて良かったのですが残念です
- 2020/05/25 標高1000m コマユミ


イロハモミジ
- 粗い鋸歯からイロハモミジとしました
- 2020/05/25 標高1050m イロハモミジ



オオモミジ
- 細かく整った鋸歯から鋸歯からオオモミジとしました
- ずく散歩のフィールドではイロハモミジよりオオモミジの方をよく見ます
- 2020/05/25 標高1100m オオモミジ(左下、中下)
- 2020/05/25 標高1200m オオモミジ(右下)



ハウチワカエデ
- 大きな葉とこの時期に種をつけているのでハウチワカエデ
- コハウチワカエデより1か月くらい早く花を咲かせるのかな ...
- 2020/05/25 標高1350m ハウチワカエデ



コハウチワカエデ
- 葉の形状、花序からコハウチワカエデでいいと思います
- ハウチワカエデの花は赤く目立つが、コハウチワカエデの花は地味ですね
- 2020/05/25 標高1450m コハウチワカエデ

2020/05/25 コハウチワカエデ
2020/05/25 コハウチワカエデ
2020/05/25 コハウチワカエデ
ヒナウチワカエデ
- ハウチワカエデとの区別に自信ありませんが ...
- 他の枝にはハウチワカエデのような葉もありましたが ...
- 葉の切れ込みに隙間があるのでヒナウチワカエデ?
- 2020/05/25 標高1400m


2020/05/21
※イヌザクラ
⇒ イヌザクラ/阿智村 絶滅
- 「阿智村の植物 レッドデータブック」では絶滅となっていますが、2018年に存続を確認
- 古木ですが2020年も元気に花を付けました/結構目立つ場所で生きていますに
- 2020/05/01 イヌザクラ蕾(左下)
- 2020/05/21 イヌザクラ開花(右下)


ツノハシバミ、サルトリイバラ(ユリ科)
- 2020/05/21 標高1100m ツノハシバミ?(左下)/ハシバミとの区別は微妙ですが ...
(葉の形状からツノハシバミでいいのかな ...) - 2020/05/21 標高1050m サルトリイバラ?(右下)
(葉の基部に巻きひげが1対あるので多分サルトリイバラで間違ってないと思いますが ...)


スノキ
- 元々小さな花ですが今年は一段と小さく感じます
- 2020/05/21 標高1100m スノキ


キイチゴ属
- これはニガイチゴorクマイチゴ?
- 2020/05/21 標高1100m

2020/05/21 キイチゴ属
2020/05/21 キイチゴ属
2020/05/21 キイチゴ属
モミジイチゴ
- 2020/05/21 標高1200m モミジイチゴ終了間近/これはモミジイチゴでしょう

2020/05/21 モミジイチゴ
2020/05/21 モミジイチゴ
2020/05/21 モミジイチゴ
コバノガマズミ
- 2020/05/21 標高1100m コバノガマズミ

2020/05/21 コバノガマズミ
2020/05/21 コバノガマズミ
2020/05/21 コバノガマズミ
オトコヨウゾメ
- 2020/05/21 標高1150m オトコヨウゾメ

2020/05/21 オトコヨウゾメ
2020/05/21 オトコヨウゾメ
2020/05/21 オトコヨウゾメ
ツルシキミ、コクサギ
- 2020/05/21 標高1450m ツルシキミ終了間近
- 2020/05/21 標高1000m コクサギ/コクサギ型(葉の付き方が2枚づつの互生)


2020年4月
2020/04/15
ミツバツツジ
- 開花が始まっても、まだ葉が出てこないのがミツバツツジ
- 2020/04/15 標高800m ミツバツツジ


2020/04/09
ミヤマチョウジザクラ
- 離れたところの花なので、ピントの合った写真が厳しいね
- 2020/04/09 標高800m ミヤマチョウジザクラ


フサザクラ
2020/04/03 標高800m フサザクラ

2020/04/03 フサザクラ
2020/04/03 フサザクラ
2020/04/03 フサザクラ
アセビ
2020/04/03 標高950m アセビ

2020/04/03 アセビ
2020/04/03 アセビ
2020/04/03 アセビ
ツルマサキ(ニシキギ科)?
山野で普通に見られる常緑のツル性木本らしいが、私は初めて認識しました。
珍しくなくても知らなかった物を知ることは、私にとっては価値のある事です。また一つニシキギ科のアイテムが増えました。(花を確認したら?を外します)
2020/04/03 標高1000m ツルマサキ(ニシキギ科)?



ツノハシバミorハシバミ
- ツノハシバミの雌花序は雄花序の上に付く
- ハシバミのの雄花序は雌花序の上に付く
理屈は判るのですが下の写真がどちらなのか判らない
2020/04/03 標高 1050m ツノハシバミ

2020/04/03 ツノハシバミ
2020/04/03 ツノハシバミ
2020/04/03 ツノハシバミ
アブラチャン
2020/04/03 標高1050 アブラチャン

2020/04/03 アブラチャン
2020/04/03 アブラチャン
2020/04/03 アブラチャン
ダンコウバイ
花が小さいこと、柱頭らしきものが見える?ので雌株(雌花序)とします
2020/04/03 標高1200m ダンコウバイ(雌花序)



花が大きいようで、柱頭が見えない?ので雄株(雄花序)とします
2020/04/03 標高 1150m ダンコウバイ(雄花序)

2020/04/03 ダンコウバイ
2020/04/03 ダンコウバイ
2020/04/03 ダンコウバイ
2020年3月
2020/03/21
- 今年は暖かいのでダンコウバイ、ツノハシバミなどの花が見れるかなと思ったのですが、ダンコウバイはあと2~3日くらい、ツノハシバミはまだまだでした。
- 結局咲いていたのは1000m位の所のアセビだけでした。いつものように光って花の写真は上手く撮れません。

2020.03.21 アセビ
2020.03.21 アセビ
2020.03.21 ツルシキミ
2020.03.21 ダンコウバイ
2020.03.21 ツノハシバミ
クルミ科
サワグルミ
- 2016/07/02 標高1000m サワグルミ(左下)
- 2016/07/15 標高1100m サワグルミ(中下、右下)



オニグルミ
2018/05/15 標高800m オニグルミ(雄花序と雌花序)

2018/05/15 雄花序(左下)は下に垂れ、雌花序(中下)は上に、2016/07/06 実(右下)は下に



ヤナギ科
- ミヤマヤナギ以外にも何種類か写真は撮っていますが、種類を調べることに難儀しています。
- 私の好きな ヤマナラシ とか イヌコリヤナギ あたりから載せていく予定
イヌコリヤナギ
- 紅葉の後半、殆どの広葉樹が落葉する頃にキレイな黄葉を見せてくれます
- (過去の写真が見つかるか、新しい写真が撮れるまで未掲載)
ミヤマヤナギ 絶滅していません ギリ生きています
- 阿智村では絶滅種にされている木本なので、はっきりとした場所は記載しませんが標高1600m位の微妙な場所で生きています。
- 細心の注意をしながらササ刈りをする植物(木本)の一つです。
2018/04/14 標高1600m ミヤマヤナギ



2018/04/28 標高1600m ミヤマヤナギ

2018/04/28 ミヤマヤナギ
2018/04/28 ミヤマヤナギ
2018/04/28 ミヤマヤナギ
2015/06/07 標高1600m ミヤマヤナギ

2015/06/07 ミヤマヤナギ
2015/06/07 ミヤマヤナギ
2015/06/07 ミヤマヤナギ
ヤマナラシ
- 大木になると見つけやすいが、写真の撮りにくい場所に生えていることが多い
- 風が吹くと葉が擦れて音がするから_"ヤマナラシ"
- 2015/10/19 標高1300m ヤマナラシ
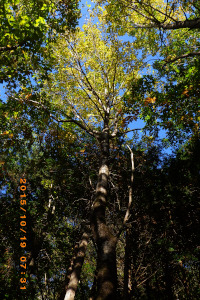
2015/10/19 ヤマナラシ
2015/10/19 ヤマナラシ
2015/10/19 ヤマナラシ
カバノキ科
シラカバ
- 2016/06/30 標高1100m シラカバ(左下、中下)
- 2017/11/01 標高1000m シラカバ(右下)

2016/06/30 シラカバ
2016/06/30 シラカバ
2017/11/01 シラカバ
コラム:シラカバとダケカンバ
- 標高1400m位でシラカバとダケカンバの雑種とみられる個体が見られます。1400m以上でダケカンバは多く見られ、 シラカバは殆ど見られなくなります。
- ダケカンバは亜高山帯の指標木の一つです。
ダケカンバ
- 2018/10/22/25 標高1400m ダケカンバ(左下、中下)/まだ若いが期待のダケカンバ
- 2014/10/28 標高1600m ダケカンバ(右下)

2018/10/22 ダケカンバ
2018/10/25 ダケカンバ
2014/10/28 ダケカンバ
ミズメ
- この辺りのカバノキ属の樹木の中では、一番の黄葉を見せてくれる
- 私はウダイカンバは間伐してもミズメは極力残すようにしています
- 2016/07/02 標高1550m ミズメ

2016/07/02 ミズメ
2016/07/02 ミズメ
2016/07/02 ミズメ
サワシバ
- 2013/06/08 標高1500m サワシバ



クマシデ
- 2017/06/27 標高1500m クマシデ




ツノハシバミ
- 図鑑等でハシバミやツノハシバミの若葉には茶色の斑が入るとありますが ...
- 葉の形状からツノハシバミなのかな?
- 若い木なので花は付けていませんが、今後花を咲かせるのを楽しみにしています
- 2017/05/21 標高1100m ハシバミ


- 雌花序が雄花序の上に付くのがツノハシバミということですが、私には分かり難い
- ただ、実になると特徴のある形なのですぐ判ります

2014/04/03 ツノハシバミ
2015/03/30 ツノハシバミ
2015/09/15 ツノハシバミ
2015/09/15 ツノハシバミ
2016/03/29 ツノハシバミ
2016/04/09 ツノハシバミ
下の写真なら私でも雌花序(赤いイソギンチャクに似ているのが雌花序)が上なのは解かります
2017/04/15 標高1050m ツノハシバミ

下の写真、雄花序と雌花序どちらが上か分かりますか_私は?
2018/03/26 標高1050m ツノハシバミ

右下の写真なら私でも雌花序(赤いイソギンチャクに似ているのが雌花序)が上なのは解かります
2018/03/26 標高1050m ツノハシバミ

2018/03/26 ツノハシバミ
2018/03/26 ツノハシバミ
2018/03/26 ツノハシバミ
下の写真は高い枝のツノハシバミを撮ったものですが、雄花序と雌花序の位置関係わかりますか
2018/03/30 標高1100m ツノハシバミ



ブナ科
ブナ / イヌブナ
- 2018/05/20 標高1650m ブナ(左下、中下)
- 2015/10/14 標高1650m ブナ(右下)



- 2017/05/21 標高1650m ブナの花(意外に沢山付くことを知りました)



- 2015/06/23 標高1550m ブナの実(左下、中下)
- 2013/06/25 標高1400m ブナの未熟な実(右下)



ブナとイヌブナの葉
- 2018/05/20 標高1650m ブナ(左下) 2013/07/16 標高1650m ブナ(中下)
- 2018/06/19 標高1250mイヌブナ(右下)

2018/05/20 ブナ
2013/07/16 ブナ
2018/06/19 イヌブナ
ブナとイヌブナの黄葉
- 2017/11/01 標高1450m ブナ(左下)
- 2017/11/01 標高1200m イヌブナ(右下)


コナラ
- 2017/05/14 標高800m コナラ



ミズナラ
- 2012/10/29 標高1600m ミズナラ
- 2015/10/22 標高1600m ミズナラ
- 2013/11/11 標高1400m ミズナラ



ヤマグリ
- 2017/06/27 標高900m ヤマグリ
- 2016/06/13 標高1000m ヤマグリ


ニレ科
ケヤキ
- 2015/10/22 標高1050m ケヤキ(左下、中下)
- 2015/10/26 標高1050m ケヤキ(右下)

2015/10/22 ケヤキ
2015/10/22 ケヤキ
2015/10/26 ケヤキ
クワ科
ヤマグワ
- 2016/07/02 標高1000m ヤマグワ



ビャクダン科
ツクバネ
- 見つけるまで何年もかかりましたが、身近にありました/完熟した実の写真もいずれ ...
- 2018/05/12 標高800m ツクバネ開花(左下、中下)
- 2017/06/07 標高800m 花後、実になり始めたツクバネ(右下)



ヤドリギ科
ヤドリギ
- カツラの枝に寄生したヤドリギ(アカミヤドリギ?)/カツラの落葉後に気が付きました
- 2017/11/17 標高1350m ヤドリギ(アカミヤドリギ?)


モクレン科
コブシとタムシバ
- 春、白い花が目立つのですが遠くからだとコブシなのかタムシバなのか区別できません
- 花の下に一枚葉がついているのがコブシ/葉が展開すれば区別は簡単
コブシ
- 2014/04/15 標高800m コブシ


タムシバ
- よく観ていけばコブシとタムシバの住み分けが判るのでしょうか?
- 2017/04/16 標高800m タムシバ(分かり難い写真ですが花の下に葉はついていない)

2017/04/16 タムシバ
2017/04/16 タムシバ
2017/04/16 タムシバ
ホオノキ
- 2018/04/20 標高1200m ホオノキ(コブシ、タムシバよりも一か月くらい遅く開花する)

2018/04/20 ホオノキ
2018/04/20 ホオノキ
2018/04/20 ホオノキ
クスノキ科
ダンコウバイ
下の写真は柱頭(多分柱頭だと思いますが)が見えているので雌花序でいいのかな(自信はありません)
2014/04/09 標高1200m ダンコウバイ(雌花序)


下の写真は柱頭がなさそうなので雄花序でいいと思います
2015/04/02 標高1200m ダンコウバイ(雄花序)


- 標高1200m以上になると殆んど見ない
- 2020/04/03 標高1100m ダンコウバイ/2020年のダンコウバイ開花(左下)
- 2014/09/22 標高1100m ダンコウバイ(特徴のある形の葉&未熟の実)
- 2015/10/22 標高1100m 写真は日当たりの悪い場所のダンコウバイだが日当たりが良ければキレイな黄葉になる(右下)

2020/04/03 ダンコウバイ
2014/09/22 ダンコウバイ
2015/10/22 ダンコウバイ
アブラチャン
子房、柱頭など見えないので雄花序なのか
2018/03/30 標高900m アブラチャン(雄花序) ↓


子房、柱頭が見えるので雌花序です
2018/04/05 標高900m アブラチャン(雌花序) ↓



- 2020/04/09 標高1050m アブラチャン/2020年のアブラチャン開花中(左下)
- 2014/09/22 標高1050m アブラチャン/未熟の実
- 2015/10/22 標高1050m アブラチャン/日当たりの良いアブラチャン(キレイな黄葉)

2020/04/09 アブラチャン
2014/09/22 アブラチャン
2015/10/22 アブラチャン
クロモジ
ダンコウバイ、アブラチャンから少し遅れて黄色い花を付ける(クスノキ科)
2016/04/19 標高1200m クロモジ

- 2015/04/27 標高1150m クロモジの開花した花と展開中の葉(左下)
- 2015/10/26 標高1450m クロモジの完熟した実(中下)/冬芽(右下)

2015/04/27 クロモジ
2015/10/26 クロモジ
2015/10/26 クロモジ
ヤマグルマ科
ヤマグルマ
- 2018/04/28 標高1550m ヤマグルマ/常緑なので落葉樹の葉が展開する前は目立つ
- 2016/06/19 標高1550m ヤマグルマ開花



フサザクラ科
フサザクラ
- 2020/04/03 標高800m フサザクラ開花
- 2016/07/15 標高1000m 葉を展開中のフサザクラ(若葉に産卵中のルリシジミ)


カツラ科
カツラ
● 2018/04/16 標高1350m 満開のカツラ(左下)__● 2017/05/19 標高1350m 新緑のカツラ(右下)



16/04/19 カツラ
18/04/19 カツラ
17/05/07 カツラ
バラ科(サクラ属/サクラ亜属) 日本の野性の桜(8種)
1. エドヒガン
2018/04/05 標高850m エドヒガン(840*300px)

- 2020/04/28 2020年終了間近の "駒つなぎの桜" (左下)
- 2018/04/17 エドヒガン開花(中下)
- 2018/04/17 標高850m エドヒガン/このエドヒガンは誰も写真を撮りに来ませんね(右下)



2. マメザクラ
- 標高1350mの沢沿いで見つけた1本です
- 花後の葉も確認してマメザクラには間違いないないと思うが、何マメザクラなのかは不明
- 2018/04/29 標高1350m マメザクラ


- 2018/04/25 標高1350m マメザクラ



3. タカネザクラ
2018/04/28 標高1600m タカネザクラ(555/255*320px)


- 標高1500m以上でよく見る桜です
- 日本の野生の桜の中で一番標高の高い所まで分布している桜

18.04.28 タカネザクラ
18.04.28 タカネザクラ
18.04.28 タカネザクラ
4. ミヤマチョウジザクラ
2018/04/10 標高800m ミヤマチョウジザクラB(840*400px)

- 標高800mの沢沿いで見つけた桜ですが、ミヤマチョウジザクラで間違いないと思います
- 岐阜県と長野県下伊那にしか分布していないチョウジザクラの変種がミヤマチョウジザクラ
- 二か所で確認しているが存続するにはどちらも厳しい環境です
ミヤマチョウジザクラA
- 2017/04/24 標高800m ミヤマチョウジザクラ
- 初めて見つけたミヤマチョウジザクラですがこの先存続していくには厳しい環境下にある
- 人の手が入る所なので仕方ない面もありますが ...何とか残していきたいね



ミヤマチョウジザクラB
- 2018/04/10 標高800m ミヤマチョウジザクラ
- この場所も人の手が入る場所ですが、話せば判っていただけるのかな~
- ミヤマチョウジザクラAよりも日当たりが良い場所にあるので一週間~10日くらいは早く開花する

2018/04/10 ミヤマチョウジザクラ
2018/04/10 ミヤマチョウジザクラ
2018/04/10 ミヤマチョウジザクラ
5. ヤマザクラ
2018/05/04 標高1380m ヤマザクラ(405*250px)


- 大きくなる桜なので、確認が難しいのですが写真の桜はまだ若木なので花の写真が撮れました。
- 花序に柄があり、毛が無いのでヤマザクラだと思います。

2018/05/04 ヤマザクラ
2018/05/04 ヤマザクラ
2018/05/04 ヤマザクラ
6. オオヤマザクラ
2018/04/26 標高1500m オオヤマザクラ(505/305*300px)


- 花、花序の特徴などからオオヤマザクラだと特定しました。

2018/04/26 オオヤマザクラ
2018/04/26 オオヤマザクラ
2018/04/26 オオヤマザクラ
7. カスミザクラ
- 花序の特徴などからカスミザクラだと特定しました。
- 2018/04/21 標高800m カスミザクラ(505/305*300px)


8. ミヤマザクラ
2018/05/18 標高1350m ミヤマザクラ(840*240px)

- 他の桜に比べると花序の特徴が異なり見分けやすい桜です。
- 阿智村では絶滅種にされていますが、標高1400mあたりで何本も確認しています。

2018/05/18 ミヤマザクラ
2018/05/18 ミヤマザクラ
2018/05/18 ミヤマザクラ
バラ科(サクラ属/ウワミズザクラ亜属・スモモ亜属)
ウワミズザクラ
2016/08/31 標高1350m ウワミズザクラ(840*200px)


2015/05/22 標高1350m ウワミズザクラ(405*200px)


イヌザクラ(古木ですが) 絶滅していませんよ
2018/05/18 標高800m イヌザクラ(405*150px)


- 阿智村では絶滅したことにされていますが(記憶に間違いがなければ)、生きています(標高800m)
- 見つけたときは花弁がほぼ落ちていましたが、花序、葉の特徴などからイヌザクラで間違いない

2018/05/18 イヌザクラ
2018/05/18 イヌザクラ
2018/05/18 イヌザクラ
スモモ
- 原則、このホームページには在来種しか写真を載せないことにしていますが、スモモは特例です
- 写真のスモモは、現在栽培されているスモモとは違い奈良時代に渡来したものが野生化したものです(多分)
- 2018/04/20 標高900m スモモA (標高1370mでも古いスモモを確認しています)

- 2018/04/20 標高1000m スモモB

2018/04/20 スモモ
2018/04/20 スモモ
2018/04/20 スモモ
バラ科(バラ属・キイチゴ属)
ノイバラ
- ノイバラの仲間も何種類もあります
- 私のスキルでは判別は難しいのですが下の写真はノイバラとしました
- 2017/06/27 標高1150m ノイバラ

2017/06/27 ノイバラ
2017/06/27 ノイバラ
2017/06/27 ノイバラ
モミジイチゴ
- キイチゴ属の中では一番早く花を咲かせるのかな/ごく普通に見るキイチゴ
- 2012/05/17 標高1350m(左下) 2014/05/02 標高1100m(中下) モミジイチゴ
- 2015/06/18 標高1100m(右下) モミジイチゴ

2012/05/17 モミジイチゴ
2014/05/02 モミジイチゴ
12/05/17 モミジイチゴ
クマイチゴ
- 名前からのイメージとは違って花弁は細い
- 2018/06/03 標高1500m クマイチゴ

2018/06/03 クマイチゴ
2018/06/03 クマイチゴ
2018/06/03 クマイチゴ
- 2013/05/26 標高1400m クマイチゴ?



ニガイチゴ
- 2018/05/18 標高1100m ニガイチゴ

2018/05/18 ニガイチゴ
2018/05/18 ニガイチゴ
2018/05/18 ニガイチゴ
- 2013/05/21 標高1400m ニガイチゴ



ミヤマニガイチゴ
- 自信はありませんがはの形状を見るとミヤマニガイチゴでいいのかな
- 2014/06/12 標高1550m ミヤマニガイチゴ

2014/06/12 ミヤマニガイチゴ
2014/06/12 ミヤマニガイチゴ
2014/06/12 ミヤマニガイチゴ
- 2014/06/30 標高1650m ミヤマニガイチゴ/花は終了している(左下、中下)
- 2013/08/18 標高1650m ミヤマニガイチゴの実/美味しいらしい(右下)



ハスノハイチゴ
- 南信州が分布の西限になるらしい/葉の形ですぐ判ります
- 標高1400~1500mくらいの場所で見るが、花を付けている個体は殆ど見ない
- ササ刈りの餌食になる木本の一つです 長野県では貴重なんですに!
- 2014/06/11 標高1350m ハスノハイチゴ



- 2013/06/25 標高1350m ハスノハイチゴ/花は終了しておりました


バライチゴ
- 標高1400mくらいまで広く分布
- 2015/08/11 標高1100m バライチゴの赤い実(左下)
- 2018/07/01 標高1100m バライチゴの大きな花(中下、右下)
- 萼片の先がやたら細く伸びていますよね(中下)

2015/08/11 バライチゴ
2018/07/01 バライチゴ
2018/07/01 バライチゴ
ナワシロイチゴ
- 花弁がピンク色なのですぐわかる/珍しい植物(木本)ではないらしい
- ナワシロイチゴ満開(中下)/乾燥の為か萼片が下方に巻き込んでいる
- 2018/06/19 標高1000m ナワシロイチゴ

2018/06/19 ナワシロイチゴ
2018/06/19 ナワシロイチゴ
2018/06/19 ナワシロイチゴ
- 右下の写真/萼片は開き花弁は開いていないがこれで満開らしいです
- 2014/06/12 標高1000m ナワシロイチゴ


*エビガライチゴ*
- 一度覚えると忘れない植物(木本)/二か所で確認
- 2018/06/19 標高1150m エビガライチゴ



- 2018/06/19 標高1150m エビガライチゴ開花(左下、中下)
- ナワシロイチゴと同じく花弁は開かない(中下)
- 2018/08/17 標高1300m エビガライチゴの実(右下)

2018/06/19 エビガライチゴ
2018/06/19 エビガライチゴ
2018/08/17 エビガライチゴ
バラ科 (ヤマブキ属・リンゴ属・ナシ属)
ヤマブキ
- 名前通りの見事な山吹色の花を付けるが普通に見るのであまり有難みを感じない
- 私はむしろ蕾の時の方が絵心をくすぐられるんですけど ...
- 2017/05/01 標高900m ヤマブキ蕾(左下)
- 2017/05/07 標高1000m ヤマブキ(中下、右下)



ズミ
- ヤマブキ同様、開花する前の白とピンクの蕾の時の方がそそられる植物(木本)です
- 2018/05/18 標高1350m ズミ蕾(左下)
- 2013/06/01 標高1350m ズミ満開/青空があればね~(中下、右下)



オオウラジロノキ
- ※自分のルールを破った唯一の写真です(お気に入りなので掲載します)
- 阿智村ではなく、ギリ境界を越えた中津川市で撮ったオオウラジロノキ
- 2015/05/29 標高1600m オオウラジロノキ



ヤマナシ
- ずく散歩のフィールドでは4本ヤマナシを確認
- 2017/05/20 標高1370m ヤマナシ満開


- 2015/10/29 標高1370m ヤマナシ/この年は豊作でした


バラ科 (カマツカ属・その他)
カマツカ
- 諸事情で沢山切らせて戴きました/皮を剥ぐと良い杖になりますに
- 2018/06/03 標高1650m カマツカ開花中


ナナカマド
- 2013/06/22 標高1600m ナナカマド開花(左下)
- 2014/10/18 標高1600m ナナカマド紅葉(右下)


コゴメウツギ
- 蕾、花、葉それぞれが他の植物(木本)と区別し易い/派手じゃないけど好きですね私は ...
- 2018/05/26 標高1100m コゴメウツギ蕾(左下)
- 2017/06/14 標高1100m コゴメウツギ開花中(中下、右下)



ユキノシタ科
ヤマアジサイ
- 2018/07/01 標高1150m ヤマアジサイ蕾(左下)
- 2018/07/01 標高1150m ヤマアジサイ開花

2018/07/01 ヤマアジサイ
2018/07/01 ヤマアジサイ
2018/07/01 ヤマアジサイ
- 装飾花の萼片の色が変化する個体もある
- 2018/07/07 標高1350m ヤマアジサイ蕾(左下)
- 2018/07/13 標高1350m ヤマアジサイ開花(中下)
- 2018/07/13 標高1350m ヤマアジサイ花後(右下)

2018/07/07 ヤマアジサイ
2018/07/13 ヤマアジサイ
2018/07/26 ヤマアジサイ
コアジサイ
- 2018/07/01 標高1450m コアジサイ開花
- 2014/11/11 標高1450m コアジサイ黄葉

2018/07/01 コアジサイ
2018/07/01 コアジサイ
2014/11/11 コアジサイ
ノリウツギと○○
- ノリウツギは普通によく見る木ですが、ここで問題です
- 右下 2013年7月16日 ノリウツギの写真を見て○○に気が付きませんか?
- 画像が悪いので見にくいかもしれませんが、よ~く見てください。
- 正解はこちら ⇒
ノリウツギ
- 2017/07/21 標高1350m ノリウツギ
- 2013/07/16 標高1450m ノリウツギ(右下)

2017/07/21 ノリウツギ
2017/07/21 ノリウツギ
2013/07/16 ノリウツギ
タマアジサイ
- 2017/07/26 標高1050m タマアジサイ蕾(左下)
- 2015/07/24 標高1050m タマアジサイ

2017/07/26 タマアジサイ
2017/07/26 タマアジサイ
2017/07/26 タマアジサイ
ツルアジサイ
- 写真のツルアジサイとイワガラミは同じ場所で撮ったもの
- 2018/06/03 標高1370m ツルアジサイ(まだ蕾)

2018/06/03 ツルアジサイ
2018/06/03 ツルアジサイ
2018/06/03 ツルアジサイ
イワガラミ
- 装飾花の萼片の数(ツルアジサイ3~4枚/イワガラミ1枚)
- 萼片はよ~く見ると白い葉に見えるよね~
- 2018/07/03 標高1370m イワガラミ(まだ蕾)

2018/07/03 イワガラミ
2018/07/03 イワガラミ
2018/07/03 イワガラミ
バイカウツギ
- 見るまでの期待感ほどではありませんでしたが、ウツギに比べて個体数が少ないので ...
- 2017/06/27 標高1150m バイカウツギ//毛が目立たない

2017/06/27 バイカウツギ
2017/06/27 バイカウツギ
2017/06/27 バイカウツギ
ウツギ
- 普通に見られる植物(木本)/ウツギに特に関心はないが昆虫にとっては重要な食糧源
- 2018/06/19 標高900m ウツギ//毛が目立つ


マメ科
フジ
- 2018/05/12 標高800m フジ



ユクノキ
- 花期とても存在感のあるユクノキ2本
- 2015/06/19 標高900m ユクノキ



アケビ科
アケビ
- 2016/05/12 標高1050m AM6時前のアケビの花/バックの青空眩し~ね~
- (アケビの雄花と雌花の違いを知らなかった頃に撮った写真です)
- 2017/09/23 アケビの完熟の実(右下)


● 2018/05/06 アケビの花序/雄花&雌花(左下)/ 雄花(中下)/ 雌花(右下)

2018/05/06 アケビ 雄花と雌花
2018/05/06 アケビ 雄花
2018/05/06 アケビ 雌花
ミツバアケビ
2018/05/05 標高800m ミツバアケビ

2018/05/05 ミツバアケビ
2018/05/05 ミツバアケビ
2018/05/05 ミツバアケビ
マタタビ科
マタタビ&ミヤママタタビ
葉が白くなるのは、これから花が咲きますよという合図かな(ミヤママタタビはピンクになります)
2016/06/19 標高900m マタタビの白葉 ↓ (405*180px) 2016/07/15 標高1500mミヤママタタビ ↓


マタタビ
- 開花時、葉が白色になる(ミヤママタタビのようにピンク色にはならない)
- 2016/06/22 標高800m マタタビ(花だけでなく萼片も白いのか ...右下)




ミヤママタタビ
- 開花時、葉がピンク色になる/白色からピンク色に変わっていくのかな ...
- 知らない時はピンクのスプレーでもかかったのかなと思っていた
- 2018/06/14 標高1570m ミヤママタタビ

2018/06/14 ミヤママタタビ
2018/06/14 ミヤママタタビ
2018/06/14 ミヤママタタビ
サルナシ
- 2016/06/26 標高11500m(左下、中下) 2017/07/02 標高11500m(右下)

2017/07/02 サルナシ
2017/07/02 サルナシ
2016/06/26 サルナシ
ユズリハ科
ユズリハ
- 2017/06/04 標高900m ユズリハ



ミカン科
ツルシキミ
- 5月の開花時を除くと蕾の時も実の時もよく似ている
- 2015/04/27(左下) 2015/05/09(中下) 2015/10/14(右下) 標高1450m

2015/04/27 ツルシキミ
2015/05/09 ツルシキミ
2015/10/14 ツルシキミ
コクサギ
- 2枚ずつ互生する"コクサギ型"と呼ばれる特有の葉の付き方をする
- 2016/04/24 標高1050m コクサギ


サンショウ
- 2017/05/21 標高1150m サンショウの黄色い花開花中(上)
- 2017/07/15 標高1150m 若い緑のサンショウの実(中)
- 2015/10/19 標高1150m 赤い実と黄葉のサンショウ(下)



ウルシ科
ヤマウルシ
- 2018/05/18 標高1400m ヤマウルシ(左下)
- 2013/06/30 標高1400m ヤマウルシ(中下)
- 2016/10/24 標高1100m ヤマウルシ(右下)



ヌルデ
- ヌルデの茎には翼がある
- 2013/07/11 標高1100m(左下) 2016/10/19 標高1050m(中下) 2016/10/19 標高1100m(右下)

2013/07/11 ヌルデ
2016/10/19 ヌルデ
2016/10/19 ヌルデ
ツタウルシ
- 2018/06/22 標高1600m ツタウルシの花(左下)
- 2017/10/09 標高1600m ツタウルシ(中下)/日陰なので紅葉の発色が悪い
- 2016/10/19 標高1600m ツタウルシ指標木(右下)/日当たり良く毎年期待を裏切りません

2018/06/22 ツタウルシ
2017/10/09 ツタウルシ
2016/10/19 ツタウルシ
カエデ科
2015/10/03 標高1550m 早紅のカエデ(840*350px)

上の写真を見ていただければ分かりますが、周りの木々が色づき始めた頃にピークの紅葉を迎える
そして周りの木々がピークを迎える前にとっとと落葉 (セッカチな楓です)
オオモミジ
- 2018/05/11 標高900m オオモミジ
- 2018/11/08 標高800m オオモミジ


- 2015/10/22 標高1100m オオモミジ



ハウチワカエデ
- 赤い花を付けた花序と開花時に展開中の葉の形(傘のような)で見分けることが出来る
- 2017/05/09 標高1200m ハウチワカエデ



コハウチワカエデ
- 2018/05/16 標高1350m コハウチワカエデ指標木(左下)
- 2018/05/26 標高1500m コハウチワカエデ(中下、右下)/ 葉が伸び切ってから開花する?



- 2018/10/06 標高1350m コハウチワカエデ指標木(左下)
- 2018/10/19 標高1350m コハウチワカエデ指標木(中下)
- 2018/10/22 標高1400m コハウチワカエデ(右下)

2018/10/06 コハウチワカエデ
2018/10/19 コハウチワカエデ
2018/10/22 コハウチワカエデ
オオイタヤメイゲツの花序
花序が下向きのカエデが多い中、オオイタヤメイゲツの雄花と両性花の混じる花序は上向きに付く
(当然、種も上向きに付きます)
● 私見 : 目を引くカエデの花 BEST3 イタヤカエデ、ハウチワカエデ、オオイタヤメイゲツ
2017/05/27 標高1550m オオイタヤメイゲツ混成花序(840*220px)

オオイタヤメイゲツ
- 2018/05/26 標高1550m オオイタヤメイゲツ
- 2018/06/12 標高1550m オオイタヤメイゲツ / 花だけでなく種も目立ちます(右下)



ヒナウチワカエデ
- 葉の切れ込みに隙間があるのでヒナウチワカエデでいいと思います
- 2015/09/20 標高1400m ヒナウチワカエデ
コミネカエデ
- 2018/05/31 標高1350m コミネカエデ / オオバミネカエデに比べ花序は長いが花は小さい(左下、中下)
- 2013/10/25 標高1570m コミネカエデ / 紅葉は緑から赤に変わる(黄色やオレンジに変わることは殆どない)



オオバミネカエデ
2018/05/15 標高1650m 新緑のオオバミネカエデ(日当たりの良い場所なので橙緑色)

- 2018/05/20 標高1650m オオバミネカエデ(左端)
- 2018/05/20 標高1600m オオバミネカエデ




ウリハダカエデ
- 2016/05/14 標高1350m ウリハダカエデ(左から3枚)/ よく観るとそれなりの花
- 2016/10/22 標高1350m ウリハダカエデ




ウリカエデ
2018/06/23 標高800m 毎年種ができると目を引くウリカエデ(花期は ...)

イタヤカエデ
● イタヤカエデは春黄色い花を咲かせ、秋は黄葉 : 黄色で始まり黄色で終わるカエデ
(花が黄色の木は黄葉し、赤い花の木は紅葉するのかな : 色素の問題でしょうね、多分)


2016年4月19日 ↑ 標高900m(600/220*200px) 駒つなぎの桜と同じ頃満開になる
2018年4月20日 ↓ 標高900m(600/220*200px) イタヤカエデの黄色い花(実際はもっとキレイです)


- 2018/04/20 標高1100m イタヤカエデ
- 2017/05/12 標高1450m イタヤカエデ / 葉を展開中(紅葉ではありません)
- 2016/10/19 標高1550m イタヤカエデ / 毎年いち早く黄葉するので目立ちます



アサノハカエデ
- カエデ科の一つとして(生物多様性)
- 2018/04/29 標高1370m アサノハカエデ


トチノキ科
トチノキ
- スギタニルリシジミの食草
- 2018/05/15 標高1000m トチノキ開花中(左下、中下)
- 2015/10/19 標高1100m トチノキ(右下) / トチノキの黄葉はこのくらいの時が好きですが...

2018/05/15 トチノキ
2018/05/15 トチノキ
2015/10/19 トチノキ
- 2014/09/22 標高1200m トチノキの実(左下、中下)
- 2015/10/22 標高1000m トチノキ(右下)/ 黄葉が進みすぎて私としてはイマイチです

2014/09/22 トチノキ
2014/09/22 トチノキ
2015/10/22 トチノキ
アワブキ科
アワブキ
- 植物としては特に興味を感じないがスミナガシ、アオバセセリの食草なので注意しています
- 2016/06/22 標高800m アワブキの花
- 2016/07/08 標高800m アワブキ葉上のスミナガシ
- 2017/06/24 標高800m アワブキとアオバセセリの巣

2016/06/22 アワブキ
2016/07/08 アワブキ
2017/06/24 アワブキ
ニシキギ科
ニシキギ科の仲間は総じて実に魅力を感じます
コマユミ(ニシキギ)
- 枝に翼がないのがコマユミ(1000m~1100mで普通に見る)、翼があるのがニシキギ(種としては同じ)
- 2016/05/23 標高1000m ニシキギ / 翼を見たのはこれ一度だけ(ニシキギは少ないのかな)
- 2018/05/11 標高1000m コマユミ開花(花弁は4枚) / 隣にツリバナもある場所
- 2017/11/01 標高1100m コマユミ完熟 / 小さいが見場のするみを付ける

2016/05/23 ニシキギ
2018/05/11 コマユミ
2017/11/01 コマユミ
マユミ(ユモトマユミ)
- 私が観ているフィールドで見かけるマユミは葉の裏に毛があるのでユモトマユミでいいかな
- 2018/06/13 標高1370m ユモトマユミ開花/花弁は4枚(左下2枚)
- 2018/06/13 標高1370m ユモトマユミ葉裏/この写真では判り難いが脈上に細かい毛が生えている
- 2014/10/16 標高1350m ユモトマユミ完熟の実(右下)




*サワダツ*
- 2017/07/11 標高1350m サワダツ/全体が緑々した感じ(左下)、暗赤色の花(中下)
- 2014/09/15 標高1350m サワダツ完熟の実

2017/07/11 サワダツ
2017/07/11 サワダツ
2014/09/15 サワダツ
ツリバナ
- 2018/05/11 標高1000m ツリバナ開花(左下、中下)/花弁は5枚
- 2017/10/04 標高1000m ツリバナの実(右下)/実は5裂し稜はない

2018/05/11 ツリバナ
2018/05/11 ツリバナ
2017/10/04 ツリバナ
オオツリバナ
- 一ヶ所で何本かしか確認できておりません
- 2017/04/14 標高1350 オオツリバナ冬芽(左下)
- 2016/06/30 標高1350 オオツリバナの未熟な実(中下)/5稜 安定感のあるフォルムがいい~ね
- 2017/09/25 標高1350 オオツリバナ完熟(右下)

2017/04/14 オオツリバナ
2016/06/30 オオツリバナ
2017/09/25 オオツリバナ
ヒロハツリバナ
- 標高1400m以上になるとよく見る
- 2020/04/09 標高1450m ヒロハツリバナ冬芽(左下)
- 2016/07/02 標高1570m ヒロハツリバナの未熟な実(中下)/4個の大きな翼
- 2013/09/12 標高1450m ヒロハツリバナ完熟(右下)

2020/04/09 ヒロハツリバナ
2016/07/02 ヒロハツリバナ
2013/09/12 ヒロハツリバナ
ツルウメモドキ
- 名前だけは知っていましたが、長い間気が付きませんでした(1400m~1600mで確認)
- 他の植物も同じですが、一度認識すると他の場所でも見つかるものです
- 2018/06/12 標高1600m ツルウメモドキ

2018/06/12 ツルウメモドキ
2018/06/12 ツルウメモドキ
2018/06/12 ツルウメモドキ
モチノキ科
アオハダ
2015/10/20 標高1400m アオハダA / まだ若い木ですが秋になると特に目立ちます

- 彼方此方に気になるアオハダがある / 好きな植物(木本)の一つです
- 2015/10/20 標高1400m アオハダA / 黄葉はとても目立ちます(落葉後の赤い実も...)



- 2018/06/03 標高1650m 新緑/蕾を付けたアオハダB
- 2018/07/01 標高1650m 開花したアオハダB
- 2016/07/02 標高1650m 開花したアオハダB



※フウリンウメモドキ
- 2014年に初めてこの赤い実の写真を撮って以来、種を特定できずにいました
- ※2020年5月24日やっとフウリンウメモドキだと特定できました/スッキリした~
今のところこの1本だけしか確認していません(少ないのかも) - 2014/09/18 標高1350m フウリンウメモドキ





ソヨゴ
- 標高1400m以上では見ない / クロソヨゴとの住み分けか
- 2015/10/22 標高1000m ソヨゴの実
- 2015/06/27 標高1000m ソヨゴ開花

2015/10/22 ソヨゴ
2015/06/27 ソヨゴ
2015/06/27 ソヨゴ
クロソヨゴ
- 今のところ一ヶ所しか確認していませんが、木は元気です
- 2018/04/28 標高1600m クロソヨゴの去年の実(左下)
- 2018/07/01 標高1600m クロソヨゴ開花(中下、右下)

2018/04/28 クロソヨゴ
2018/07/01 クロソヨゴ
2018/07/01 クロソヨゴ
ハイイヌツゲ
- イヌツゲとハイイヌツゲの区別は難しいと思うのですが ...
- 2013/07/16 標高1500m ハイイヌツゲ


ツルツゲ
- 標高1400m以上にならないとお目にかかれません
- 2015/05/29 標高1500m ツルツゲ


ミツバウツギ科
ミツバウツギ
- 2018/05/11 標高900m ミツバウツギ(左下)
- 2018/05/13 標高800m ミツバウツギ(中下、右下)

2018/05/11 ミツバウツギ
2018/05/13 ミツバウツギ
2018/05/13 ミツバウツギ
シナノキ科
シナノキ
- 2016/05/20 標高1600m シナノキ若葉(左下)
- 2016/07/11 標高1600m シナノキ開花(中下、右下)

2016/05/20 シナノキ
2016/07/11 シナノキ
2016/07/11 シナノキ
キブシ科
キブシ
- 2017/04/24 標高1100m キブシの花が撮りごたえを感じないのは何故なのか
- 2014/09/22 標高1100m キブシはまだ実の方が存在感がある
- 2015/10/19 標高1150m 秋のキブシは錆色 / どの季節も地味な植物(木本)です

2017/04/24 キブシ
2014/09/22 キブシ
2015/10/19 キブシ
ウリノキ科
ウリノキ
- 葉も花もチョッチネ~きれを感じない...植物(木本)
- 2016/06/19 標高900m ウリノキ

2016/06/19 ウリノキ
2016/06/19 ウリノキ
2016/06/19 ウリノキ
ミズキ科
ミズキ
- 2015/06/12 標高1370m ミズキの花(左下)
- 2015/10/21 標高1370m 秋オレンジ色のミズキの葉


2017/05/31 標高900m ミズキ / 遠くから見てもよく判る(枝の張り方、花の付き方に特徴あり)

ウコギ科
コシアブラ
- 2016/05/14 標高1400m コシアブラ(左下) / 信州人は展開を始めた葉を好んで食します(写真の葉は成長しすぎたかな)
- 2015/10/14 標高1550m 他にはない色 / 淡い黄葉のコシアブラ
- 2015/10/19 標高1650m 青空があれば落葉後のコシアブラももなかなかのものでしょ~

2016/05/14 コシアブラ
2015/10/14 コシアブラ
2015/10/19 コシアブラ
ハリギリ
- ハリギリの幼木 / 成木は大きくなるので写真を撮りにくい
- 2018/06/23 標高900m(若い時は茎に刺があるが成長と共になくなる)

2018/06/23 ハリギリ
2018/06/23 ハリギリ
2018/06/23 ハリギリ
*ハリブキ*
- 気に掛けている植物の一つです / 全木トゲだらけの小木(ササ刈りの時に気を使っている)
- まだ花を見ていないので、いつか花を付けたハリブキを見てみたいですね~
- 2018/05/15 葉を展開中のハリブキ(左下) / 中下と同じ株
- 2017/06/14 ハリブキを確認しているのは二か所だけ(中下、右下)

2018/05/15 ハリブキ
2017/06/14 ハリブキ
2017/06/14 ハリブキ
ツツジ科
ヤマツツジ
- レンゲツツジとは葉が全く違う/花は二回り小さく丸い感じかな
- 2018/04/30 標高800m 開花を始めたヤマツツジ(標高800m~1300mくらいで普通に見られる)


ミツバツツジ
ミツバツツジの雄蕊は5個が標準
2018/04/20 標高1100m ミツバツツジ

2018/04/29 標高1400m ミツバツツジ ↓ (このエリアでは一本だけ、トウゴクミツバツツジは20本位)



2018/04/29 1400m ミツバツツジ 雄蕊が5個(標準タイプ) ↑
2017/04/24 800m ミツバツツジ 雄蕊が6個のタイプ ↓



2016/04/19 1100m ミツバツツジ 雄蕊が6個のタイプ ↓


ミツバツツジとトウゴクミツバツツジを比較して
ミツバツツジは満開の頃にはまだ葉が出ていないか出始め:
トウゴクミツバツツジは満開の頃には葉が出ている/合ってるかな?
トウゴクミツバツツジ
トウゴクミツバツツジの雄蕊は標準で10個(実際に見ていると8個、9個のものもある)
このエリアではトウゴクミツバツツジは20本くらい、ミツバツツジは一本だけしか確認していない
標高が高くなるとトウゴクミツバツツジが優先するのだろうか?
2018/04/29 標高1400mのエリア トウゴクミツバツツジ(雄蕊は9個でした) ↓


2018/05/06 標高1400mのエリア トウゴクミツバツツジ ↓

2018/04/21 800m トウゴクミツバツツジ ↓



レンゲツツジ
- 植林されたヒノキの際で細々と生きています/1650m辺りの笹原でも6月になると花を見れます
- この場所ではヤマツツジと混成しているが、花の区別は一度出来れば簡単です
- 2018/05/18 標高1200m レンゲツツジ

2018/05/18 レンゲツツジ
2018/05/18 レンゲツツジ
2018/05/18 レンゲツツジ
キョウマルシャクナゲ
- 個人的には、あまり魅力を感じる植物(木本)ではありませんが
- 環境省の絶滅危惧Ⅱ類(VU)/長野、静岡、愛知辺りにしか分布していないようですので大切に
- 2018/05/18 標高1400m キョウマルシャクナゲ

2018/05/18 キョウマルシャクナゲ
2018/05/18 キョウマルシャクナゲ
2018/05/18 キョウマルシャクナゲ
バイカツツジ
下の写真は輪生した葉を下から覗いて見えるバイカツツジの蕾
2017/06/13 標高800m(840*220px)

・バイカツツジが多い(800m~1400mで確認)のは知っていたのですが、何年も確認できない木でした
・右下の写真を見ていただければ分かるように、葉の下に隠れるように花を付けるからです
・2017/07/11 標高800m(左下、中下) ・2017/07/15 標高1400m(右下)

17/07/11 バイカツツジ
17/07/11 バイカツツジ
17/07/15 バイカツツジ
ホツツジ
● ホツツジは紅葉の景色には外せないアイテムです
● 2017/07/27 標高1600m 雨後のホツツジの花 ↓ ● 2017/08/03 標高1600m 雨後のホツツジの花 ↓


2016/10/19 標高1650m ホツツジの紅葉


ウスギヨウラク
- 1400m~1600mくらいで普通にあちこちで見るツツジ
- 2018/04/29 標高1400m ウスギヨウラク


コヨウラクツツジ
- 標高1600m辺りで見ています/写真の場所ではハナヒリノキ、ミヤマシグレと混成
- 2018/05/06 標高1600m コヨウラクツツジ


ネジキ
- 一つ一つの白い花はキレイですが花序に花が多すぎて私には綺麗に見えません(アセビも同様)
- 2013/07/09 標高1400m ネジキ


アセビ
- 野性のアセビは崖にへばりつくように生えているので
- コンパクトデジカメで写真を撮る時は、十分注意しないと危険です
- 2020/04/03 標高950m アセビ / 馬酔木と書くくらいですから有毒


ハナヒリノキ
- 標高1600m以上で普通に見られるが、標高の低い場所では見ることはできません
- どうしても見たい植物(木本)ではないかもしれないが/これもツツジ科の植物(木本)の一つ
- 生物の多様性を考える時、大切なひとつのアイテムです(キレイではないが紅葉時、独特の色合いになる)
- 2013/06/29 標高1650m ハナヒリノキ


サラサドウダンとベニドウダンの住み分け?
私が観ている限りでは、同じ場所で混成している2種を見たことがない
サラサドウダン
- サラサドウダンは標高1550m以上にならないと見たことがない
- 2018/06/03 標高1650m サラサドウダン

2018/06/03 サラサドウダン
2018/06/03 サラサドウダン
2018/06/03 サラサドウダン
ベニドウダン
- この場所(1400mの尾根筋)では、他に7~8種類のツツジ科の植物(木本)を確認しているが
- サラサドウダンは見たことがない/標高の問題か ...
- 2018/05/15 標高1400m ベニドウダン


オオバスノキ、スノキ、ウスノキについて
- オオバスノキとスノキは種としては同じだが
- 母種のオオバスノキが標高の高い所、スノキは標高の低い所に生育する
- ウスノキは萼筒に5個の稜があることで区別できる
オオバスノキ
- 余裕が出来ればスノキとの違いを数値で比較してみます
- 2018/05/20 標高1600m オオバスノキ(母種)開花中/(萼筒に稜はない)

2018/05/20 オオバスノキ(母種)
2018/05/20 オオバスノキ(母種)
2018/05/20 オオバスノキ(母種)
スノキ
- オオバスノキに比べると花も葉も小さいらしい/言われるとそうかも ...
- 2018/04/30 標高1100m スノキ(右下の写真/萼筒に稜はない)

2018/04/30 スノキ
2018/04/30 スノキ
2018/04/30 スノキ
ウスノキ
- 標高1650mでもウスノキを確認しています/近い場所でオオバスノキも確認している
- 2018/05/10 標高1350m ウスノキ(右下の写真で萼筒に稜があることがが判ります)

2018/05/10 ウスノキ
2018/05/10 ウスノキ
2018/05/10 ウスノキ
アクシバ
- 木の種類を調べ始めた頃、アクシバの蕾、花を見て感動した。(アクシバは日陰を好む小木)
- 下の写真のアクシバはとても日当たりの良い場所にある
- 元々はササが直射日光を遮る環境下で調子が良かったのだが、ササ刈りで日が当たりすぎ疲弊した
- 小さいけれどいい花を付けるんだけどね、アクシバは ...勿体無い_と私は思いますが
- 2017/07/27標高1550m アクシバ


- 2015/07/11 標高1570m 状態の良いアクシバの蕾(左下)
- 2015/07/20 標高1500m 状態の良いアクシバの花(右下)


リョウブ科
リョウブ
- 写真は富士見台の山頂付近のリョウブ/大きくなれないまま花を付けている
- 2015/07/24 標高1700m リョウブ

2015/07/24 リョウブ
2015/07/24 リョウブ
2015/07/24 リョウブ
- 2013/06/25 標高1350m リョウブ/切っても切っても枝を出すタフな植物(木本)


エゴノキ科
オオバアサガラ
2013/07/03 標高1350m オオバアサガラ(梅雨時に開花するので写真撮りにくいよね~)



エゴノキ
- 2014/06/21 標高1150m エゴノキの花(左下、中下)
- 2014/09/27 標高1150m エゴノキの実(右下)

2014/06/21 エゴノキ
2014/06/21 エゴノキ
2014/09/27 エゴノキ
ハクウンボク
● 2020/04/03 標高1150m 毎年この時期ハクウンボクの若枝の皮が剥がれてくるのは何故でしょう~

- 2015/03/30 標高1150m ハクウンボク冬芽
- 2016/05/12 標高1150m ハクウンボク
- 2016/06/05 標高1150m ハクウンボクの花



コハクウンボク
- 葉の形状が独特なので判りやすい
- 2015/10/22 標高1450m コハクウンボク黄葉(左下)
- 2016/06/11 標高1350m コハクウンボク開花(中下、右下)

2015/10/22 コハクウンボク
2016/06/11 コハクウンボク
2016/06/11 コハクウンボク
- 風景のページ 2013/06/25 の正解はコハクウンボクです
- 2013/06/01 標高1350m コハクウンボク成木の葉(左下、中下)
- 2013/06/25 標高1400m コハクウンボクの幼木(右下)



ハイノキ科
タンナサワフタギ
- サワフタギも自生している筈ですが、この写真はタンナサワフタギであっていると思います
- 2013/06/22 標高1300m タンナサワフタギ

2013/06/22 タンナサワフタギ
2013/06/22 タンナサワフタギ
2013/06/22 タンナサワフタギ
モクセイ科
アオダモ
- アオダモの仲間も何種類かありますが、取り敢えずアオダモとしました
- 2018/05/16 標高1370m アオダモ



ミヤマイボタ
- 初めて認識した時はオ~と思ったのですが、このエリアでは彼方此方で見られます
- 2018/07/03 標高1350m ミヤマイボタ

2018/07/03 ミヤマイボタ
2018/07/03 ミヤマイボタ
2018/07/03 ミヤマイボタ
クマツヅラ科
ムラサキシキブ
- コムラサキ、ヤブムラサキなどもあると思いますが今の私には識別できません
- 2015/06/29 標高800m ムラサキシキブ開花中(左下、中下)
- 2013/10/31 標高1400m ムラサキシキブの実(右下)

2015/06/29 ムラサキシキブ
2015/06/29 ムラサキシキブ
2013/10/31 ムラサキシキブ
クサギ
- 匂いに鈍感な私でもクサギの匂いは感じます
- 2013/08/13 標高1100m クサギ


フジウツギ科
フジウツギに拘る訳
仲間のフサフジウツギ(ブットレア)がチョウを集めると聞き、フジウツギにも注目していました
フジウツギ
2012/08/16 標高1500m フジウツギ(初めて見たフジウツギですがこの後6年見ることはなっかた)


- 2012年に見た場所とは近いが、2018年に6年ぶりに別の場所で見つけたフジウツギ
- 2012年に見たものと少し雰囲気が違いますが ...
- 2018/07/27 標高1400m フジウツギ(意外な場所でした/先入観がなければ何年も前に見つけていたかも)

2018/07/27 フジウツギ
2018/07/27 フジウツギ
2018/07/27 フジウツギ
スイカズラ科
ニシキウツギ
- 2018/06/12 標高1400m ニシキウツギ(左下)
- 2015/06/23 標高1350m ニシキウツギ(右下)


○○ウツギ(ニシキウツギ?orタニウツギ?)
- ニシキウツギなのか違うのか判断できない(スイカズラ科の木本であることは間違いない)
- 2018/06/16 標高1400m ○○ウツギ
スイカズラ
2017/06/13 標高800m スイカズラ(白から黄色へと変わっていく花を金銀花というらしい)


ツクバネウツギ
- 2013/06/14 標高1500m ツクバネウツギA (右下2枚)
- 2013/06/14 標高1600m ツクバネウツギB (左下2枚)




ガマズミ
- ガマズミは毛むくじゃら(ミヤマガマズミ、コバノガマズミにはほとんど毛がない)
- 2018/05/06 標高1000m(左下) 蕾、2017/06/22 標高1000m(中下) ガマズミの花
- 2017/08/30 標高1350m(右下) ガマズミの赤い実

2018/05/06 ガマズミ
2017/06/22 ガマズミ
2017/08/30 ガマズミ
ミヤマガマズミ
- 2018/06/02 標高1400m ミヤマガマズミ
- 2018/05/06 標高900m ミヤマガマズミ

2018/06/02 ミヤマガマズミ
2018/05/06 ミヤマガマズミ
2018/05/06 ミヤマガマズミ
コバノガマズミ
- 2018/04/22 標高800m(左下) コバノガマズミ(蕾の時の方が花序の構造が判り易い)
- 2018/05/02 標高800m(中下、右下) 開花中のコバノガマズミ

2018/04/22 コバノガマズミ
2018/05/02 コバノガマズミ
2018/05/02 コバノガマズミ
オトコヨウゾメ
- 1200m以上では見た記憶がない
- 2018/04/30 標高800m オトコヨウゾメ(左下2枚)
- 2013/05/29 標高1100m オトコヨウゾメ(右下2枚)




ミヤマシグレ
- ミヤマシグレが私にガマズミ属の木の特徴を教えてくれました。
- ガマズミ、ミヤマガマズミ、コバノガマズミ、オトコヨウゾメの花序をよく観るとガマズミ属の特徴が判る人には判ります。
ミヤマシグレ
- 1600mくらいでササなどの日陰に依存している
- 2018/06/22 標高1600m 満開のミヤマシグレ

2018/06/22 ミヤマシグレ
2018/06/22 ミヤマシグレ
2018/06/22 ミヤマシグレ
ムシカリ
- 1400m以上でよく見る
- 2013/11/11 標高1400m ムシカリ
- 2016/05/12 標高1550m ムシカリ

2013/11/11 ムシカリ
2016/05/12 ムシカリ
2016/05/12 ムシカリ
ニワトコ
- 800m~1600mまで広く分布している
- 2018/05/26 標高1570m ニワトコ(左下)
- 2017/07/17 標高1350m ニワトコ(右下)


ユリ科
*サルマメ*
- 木なのに見落としてしまうくらい存在感がありません。でもよく見ると花がい~いんです
- 写真のサルマメは車道横にあったのですが、2019年に刈られてしまいました。復活を期待しています。
- 2018/05/13 標高800m サルマメ

2018/05/13 サルマメ
2018/05/13 サルマメ
2018/05/13 サルマメ
マツ科
ゴヨウマツ
- 2018/06/12 標高1650m ゴヨウマツA


- 2017/10/09 標高1600m ゴヨウマツB



ヒノキ科
ヒノキ
- 周りの環境から、これは多分天然のヒノキだと思いますが ...
- 2020/05/25 標高1400m ヒノキ

2020/05/25 ヒノキ
2020/05/25 ヒノキ
2020/05/25 ヒノキ
サワラ
2017/05/03 標高1550m サワラ


イチイ科
イチイ
2015/05/28 標高1350m イチイ


正解
● 正解は右下の写真です。
● 2019年に写真の整理をするまで全く気が付きませんでした。
● 何気にノリウツギの写真を撮ったら花序と全く同じ色をしたイモムシが写りこんでいました。
○ 珍しいチョウや植物を見つけた時も感動しますが、私はこういう何気ない自然を見つけた時も
小さな感動を覚えます。


 ZUKU SANPO
ZUKU SANPO




