 |
 �Q�� |
|
 ����� |
 |
|
 ���� |
 �u�� |
|
 �u�� |
||
 �u���G�z |
 �{�� |
�����R�ϐ������Ƃ����V��@�̂����B
�V���I�㔼�A�V�q�V�c�̔���ŁA��Ė��V�c�̋��{�̂��ߑn�����ꂽ�B
�����܂Ŗ�W�O�N������A�V��18�N�i746�j�Ɋ������{���s��ꂽ�B
�ޗǂ̓��厛�A����̖�t���ƂƂ��ɓV���O���d�ƌĂꂽ�B
 �V���ΉP |
 �d���S�b |
 |
 �ߓ� |
 �@���� |
|
 ���ω��� �i�]�ځj |
 ���{�ŌÂ̓��߁i�]�ځj |
�Ő����ɂ�49���̎q�@��i�����Ƃ����܂����A�������j�̒��ōr�p�B
�����A�u���Ƃ��ɏĎ��������A�u���͉���8�N�i1680�j�A�����ˎ�E���c���V�ɂ��Č��B
�����͊��i9�N�i1631�j���������c���V�ɂ��Č����ꂽ�B
�ϐ������̕ɂ͑����̕������͂��ߕ��������c��B
 ���� |
 |
 |
 �� |
 |
 �d�Γ� |
 |
 �Γ��ܗ֓��ق� |
�ޗǎ���ɂ͊ϐ������ɉ��d�@���u���ꂽ�B
���d�Ƃ͑m�������ׂ�������������Ƃ���ł������B
�{���͜I�ɓߕ��ŕ�������̍�ŏd�v�������Ɏw�肳��Ă���B
 �{�� |
 �{���G�z |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 �n����F |
||
 ���Q |
 �M�\�� |
�]�ˎ���Ɋϐ��������痣��A���݂͑T�@�ƂȂ��Ă���B
���\16�N�i1703�j�A�����ˎ�E���c���V�̔˖��ɂ��A
�����T�@�̊Ǘ����ɂ�����A�ϐ��������痣�ꂽ�B
���݂͗ՍϏ@���S���h�̑T���B
 |
 |
 ������ |
 �����̖� |
 ���� |
 ���� |
 |
 �ߓ� |
�{���I�ɓߕ��͓��������12���I������̍�Ƃ����A���̏d�v�������ɂȂ��Ă���B
�e���A���ӕ�F�A�����F�͋��Ɏs�̕������ɂȂ��Ă���B
�{�w���w�͍���50�p�قǂ̐Ή��d�ɂȂ��Ă���B
�Γ��E�ܗ֓��͊J�R�E�Ӑ^�a��̋��{���ȂǕ������������c��B
 |
 |
 �炩�� |
 |
 ���c�F��_ |
 �Q�� |
 |
 |
 �q�a |
 �q�a���� |
 ���� |
 �̔� |
���͐퍑����̊��i�Ɠ`������_�ЂŁA�Ր_�͉��m�V�c�B
��{�n��̎��_�Œn���̐l�X�ɂ���đ���J���Ă����B
�V�����u�ߘa�v�̋N���ɂȂ����u�~�Ԃ̉��v���s��ꂽ�B
�唺���l�@��Ղ̌��n�̈�ɂȂ��Ă���B
�u���t�����A�C�i���a�v���u���t�W�v�ɂ���E�E�E
 ���t�̔� |
 ��L�� |
 �e�a�ՂP |
 �e�a�ՂQ |
 �{�a�� |
 |
 |
 |
 ���O�� |
 ���O�� |
 ��a�� |
��ɕ{�����͂V���I�`�P�Q���I�㔼�ɂ����āA
��B������s���@�ւƂ��Ă̖������ʂ������B
�n���I�ɓ��{�̊O���Ɩh�q�̍őO���ŁA�A�W�A�̑����Ƃ��Ă��@�\�������Ƃ���A
�d�v�Ȑ����̒��j�Ƃ��đ�ɕ{�̒��S�n�Ɍ��݂��ꂽ�B
�����͓쑤�𐳖ʂƂ��A��̐Βi��o��Ɠ��ՂŁA
����ɐi�ނƒ���Ղ̑b������A���������L������Ă��܂��B
�����ɘe�a�����Ă��A���ʂɂ͐��a�̐Ւn������A�b���c��B
 ��ɕ{������ |
 |
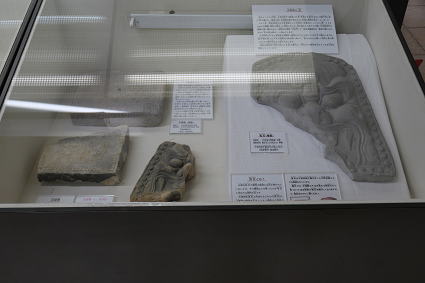 ���l�A�i����j�ق� |
 �ۊ��E�������ق� |
 �Α� |
 �����̎d������ |
 �؊Ȃق� |
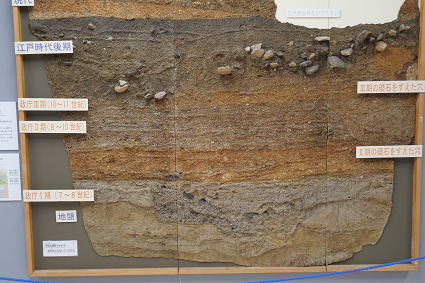 ��ɕ{�����̓y�w |
��ɕ{�W���قł͑��ɕ{�j�Ղ̔��@�����ɂ����
���o���ꂽ��\�̈ꕔ�ۑ��A���J�����Ă���B
�o�y�╨��͌^�Ȃǂő�ɕ{�̗��j�ƕ������Љ�Ă���B
 �����̑V |
 ���q�����㕔�j�ق� |
 ���q�ق� |
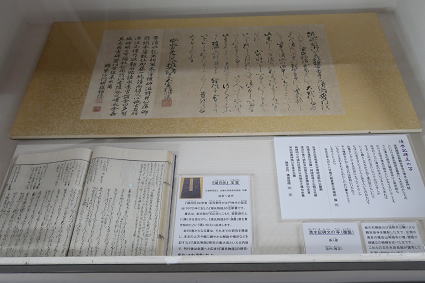 �Ό����i��顁j�O�E�ق� |
 �n���y��i���j |
 �n���y��i����j |
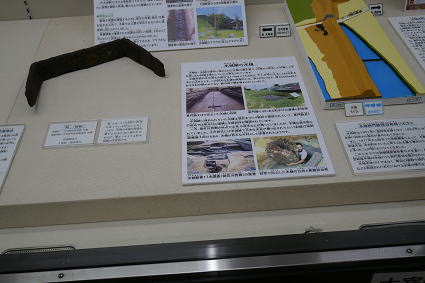 ���������i�����j |
 �S�� |
��ɕ{�����Ղł͓����̈╨�����X�o�y���Ă���B
���z�W�ł͉��������͂��߁A�����A�����ȂǁA
����ނł͂��������ȂǓ����̌��z����c��B
���̂ق��A�M�A�t�A�قȂǂ̓y����E�E�E
 �ʐa |
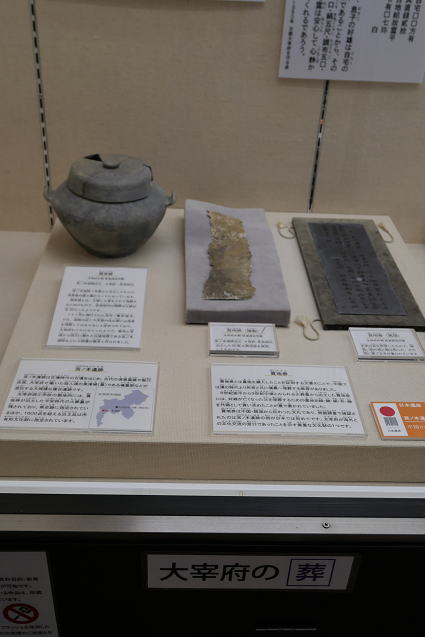 ��ɕ{�̑� |
 ���ۊ��E������ |
 �������i����j�o�y�i �������i����j�o�y�i |
 �����C��ق� |
|
 ���֓���Z���فi��E�j�ق� |
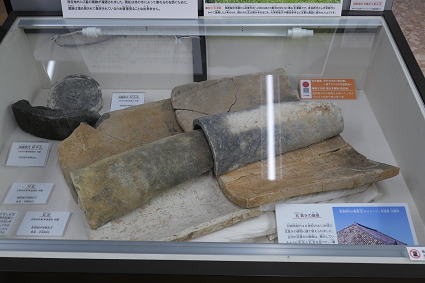 �������� |
| ��ɕ{�W���قR ��ɕ{�̈�\�Ƃ��Ă͋ʐa�i�����j�� ��ɕ{�����̓����̒n�w�Ȃǂ��W������Ă���B �����̕i�X�ɂ��A�����̑�ɕ{�̗l�q���_�Ԍ��邱�Ƃ��o����B |
|
| �����Ñ�j�T�K�̗� �P�����s���P�@�Q�����s���������@�R�@����В��Ë{�i�哇�j�@�S�D�@����ЕӒË{�@�T�D�������A�z�R�Õ��Q |
|
| �U�D�{�n�Ԑ_���@�V�D���ŋ{�ق��@8�D���c�_�Ђق��@9�D��ɕ{�V���{�P�@10�D ���ɕ{�V���{�Q�@�D | |
| 11�D��B���������قQ�@12�D��ɕ{�S�@13�D |
 |
����^�J�q�̃z�[���y�[�W |
||
 |
���삳�̃z�[���p�[�W |
||
 |
����Ƃ�ۈ玺�̃z�[���y�[�W |
||
| �g�b�v�y�[�W�� | |||
|
