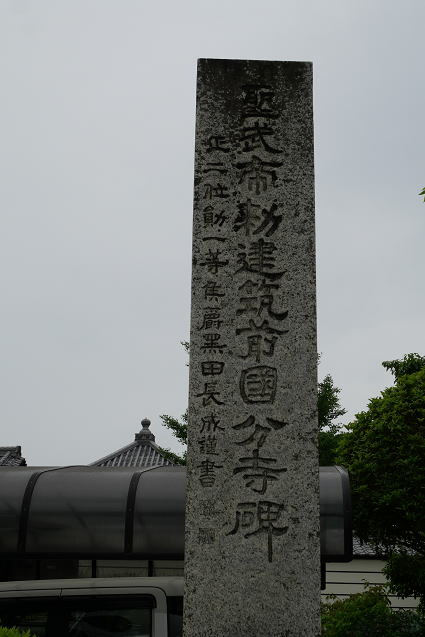|
 |
|
 |
 |
|
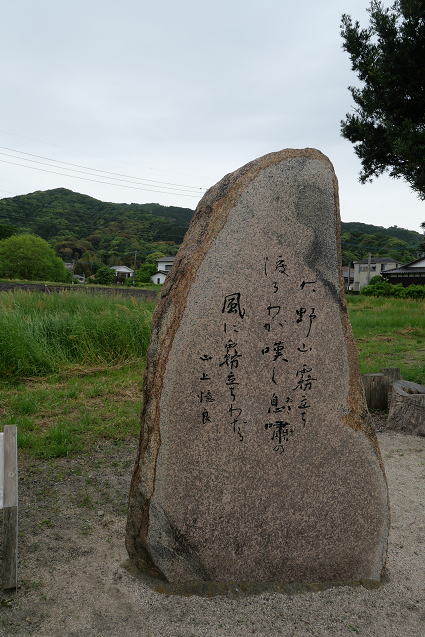 万葉集歌碑 |
 手水石 手水石 |
国分という地名は天平13年(741)に聖武天皇の詔により建てられた筑前国分寺による。
この地には国分尼寺跡、国分瓦窯跡などがあります。
国分天満宮は筑前国分寺跡に隣接してある。
 狛犬(吽形) |
 狛犬(阿形) |
|
 拝殿 |
 拝殿内部 |
|
 本殿 |
 境内社 境内社 |
国分天満宮はかつての「ムラ」の住民により祀られている。
祭神は菅原道真で、成立年代や由緒については詳しくは不明。
本殿に「弘化(1844〜47)とあることからおよそ170年前から祀られていることが分かる。
境内には万葉歌人・山上憶良の歌碑が建つ。
|
奈良時代、聖武天皇により全国に造られた国分寺の一つ。
金堂、講堂、七重塔、南大門などを回廊で結んでいる。
塔跡だけでも一辺17.4mあり、全体の壮大さがしのばれる。
七重塔(復元)は近くの大宰府ふれあい館に復元されている。
 |
 石灯籠 |
 |
 山門 |
 つくばい |
 羅漢像 |
 石仏 1 |
 石仏2 |
龍頭山筑前国分寺という高野山真言宗のお寺。
奈良時代、天平13年(741)、聖武天皇は仏教による地方政治の安定と
文化交流を図るため、国ごとに国分寺と国分尼寺の建立を命じた。
当寺も筑前国分寺として創立された。
 石仏群1 |
 石仏群2 |
 仏像群 |
 観音堂 |
 宝篋印塔 |
 |
 産安地蔵 |
 庚申塔 |
当初は豪華を極める大寺院で、その広さは現在境内に残る
大きな柱の礎石にも容易にうかがえる。
その後、廃絶近くまで荒廃したが、
天文年間(1736)に中興の師、俊了が小堂を建立した。
 |
 本堂扁額 |
 金堂礎石 |
 軒瓦 |
 |
 |
江戸時代の天明年間(1781)、僧・忍龍が山門修理の傍ら、
福岡黒田藩の長老・黒田美作より田地の寄付を受けた。
本尊は薬師如来で、行基の作といわれ、重要文化財になっている。
 |
|
 祠 |
 石仏 |
 |
 |
 水城館 |
 礎石? |
 |
 水城頂上 |
 水城からの眺め 水城からの眺め |
 |
 |
 水城疎水渠跡 |
天智2年(663)、白村江の戦いに敗れた後、
唐、新羅からの攻撃に備えて築かれた防衛施設(人工の土塁・国特別史跡)
全長約1.2km、幅約80m、高さ約13っもの巨大な土塁。
当時は東西2か所だけに門があり、門からは官道(古代の公道)が通じており、
古代の迎賓施設・鴻臚館と都が繋がっていた。
| 福岡古代史探訪の旅 1福岡市内1 2福岡市立博物館 3宗像大社中津宮(大島) 4.宗像大社辺津宮 5.鎮国寺、奴山古墳群 |
|
| 6.宮地嶽神社 7.香椎宮ほか 8.櫛田神社ほか 9.大宰府天満宮1 10. 太宰府天満宮2 . | |
| 11.九州国立博物館2 12.大宰府4 13.大宰府5 14. |
 |
福川タカ子のホームページ |
||
 |
福川さんちのホームパージ |
||
 |
しらとり保育室のホームページ |
||
| トップページへ | |||
|


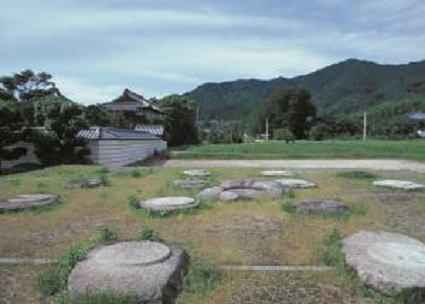 礎石
礎石