 |
 |
|
 |
 鳥居 |
|
 狛犬1(吽形) |
 狛犬1(阿形) |
|
 境内 |
 |
|
 狛犬2(吽形) |
 狛犬2(阿形) |
|
第15代応神天皇御降誕の聖地という。
「日本書記」に「皇后、新羅より還りて、誉田天皇を筑紫の蚊田に産み給う、
名付けて、宇弥という」とある。
主祭神は神功皇后、応神天皇の母子神、
玉依姫命、住吉大神、伊弉諾命の五柱を祀る。
 狛犬3(吽形) |
 狛犬3(阿形) |
 献灯籠 |
 |
 |
 中門 |
 |
 拝殿 |
敏達天皇時代(572〜586)に創建されたという。
八幡様は殖産文化の祖神として崇敬されているが、
当宮は特に「安産、育児」の信仰が厚く、
多くの人々の安産祈願や初宮詣に参拝されている。
 狛犬4(吽形) |
 狛犬4(阿形) |
 拝殿屋根 |
 拝殿正面 |
 拝殿内陣 |
 |
 子安の木(槐) |
|
 本殿 |
 衣掛の森 |
境内には古木が立ち並び、多くの古木が残る。
社殿に向かって右に「湯蓋の森」があり、
社殿の左側には「衣掛の森」がある。
共に素晴らしい老樟で、共に樹齢2000年以上といわれ、
当宮のシンボルになっている。
 |
 |
||
 |
 うぶゆの水 うぶゆの水 |
||
 湯方社 |
 子安の石 |
||
 子安台 |
 武内神社 |
||
 恵比須神社 |
境内には助産婦の祖神・「湯方社」があり、
それを取り囲むように玉垣を築き、こぶし大の石が積まれている。
安産祈願でここの石を持ち帰り、目出度く安産すると、
新しい石に子供の成長を願い、一緒に納めるという習わしがある。
 狛犬5(吽形) |
 狛犬5(阿形) |
 聖母宮 |
 生母宮拝殿 |
 |
 湯蓋の森 |
 神楽殿 |
|
 神馬 |
 |
神功皇后は産所を蚊田の邑に定め、
側に生え出づる槐の木の枝に取りすがり、応神天皇を安産にてお産みになった。
このことから「子安の木」と称され、この木にすがって安産するという信仰が生まれた。
境内奥には応神天皇が産湯に使ったといわれる「産湯の水」がある。
 |
|
 文字土器1 |
 文字土器2 |
 大野城跡礎石1 |
 大野城跡礎石2 |
 馬の絵が描かれた提瓶 |
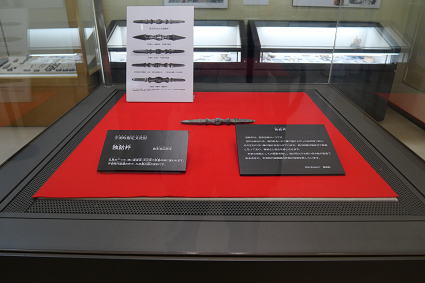 独鈷杵 |
 各地の黒曜石1 |
 各地の黒曜石2 |
 石槍(未成品)ほか |
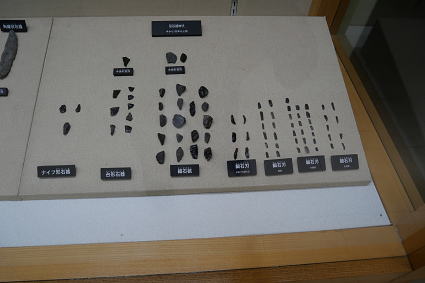 細石刃(右)ほか |
大野城は白村江の戦いに敗れ、唐、新羅軍の侵攻に備えて、天智4年(665)に築造された。
大野城跡礎石は宇美町側の百間石垣付近にあった礎石。
百間石垣は大野城跡最大の石垣で全長約180mもあった。
 石斧ほか |
 石匙(中央下)ほか |
 砥石(右下)ほか |
 弥生時代のどんぐりと米ほか |
 永楽通宝ほか |
 顔が描かれた土器ほか |
 天園遺跡出土品1 |
 天園遺跡出土品2 |
 刀子ほか |
 馬具金具ほか |
旧石器時代の遺跡は宇美公園や浦尻遺跡などで、
黒曜石などでできた石槍やナイフ形石器などが発見されている。
縄文時代のものでは浦尻遺跡や光正寺遺跡などで、
石鏃や石匙などが発見されている。
 素環頭大刀 ほか |
 馬具飾金具ほか |
 鉄剣ほか |
 高坏(白)ほか |
 鉄剣ほか |
 内行花文鏡〈中央上)ほか |
 釧ほか |
 装身具各種 |
 文字瓦 (中央)ほか |
 大野城跡出土品 |
川原田・供田遺跡や上角遺跡などで住居跡や高床式の
建物跡や井戸などが発掘されている。
遺跡からは土器のほか石剣、石戈などの武器や
紡錘車や石斧、石包丁などが出土している。
 土師器、須恵器 |
 紡錘車、臼玉ほか |
|
 高坏、壷 |
 円筒埴輪 |
|
 朝顔型埴輪 |
 土器館 |
|
 石棺石材(前)ほか |
 甕棺 |
| 宇美町立歴史民俗資料館4(弥生時代〜古墳時代) 今から約1800年前、日本は小さな国が各地にありました。 「魏志倭人伝」の中に「不弥国」という国名が書かれていますが、 宇美町を中心とした一帯ではないかといわれている。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 宇美町立歴史民俗資料館5 糟屋郡内には現在7基の前方後円墳がありますが、 その中でも最大級の光正寺古墳は 「不弥国」の国王の墓ではないかといわれている・・・ |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 宇美町立歴史民俗資料館6 宇美町にも古代より色々な動物が生存していた。 ゾウの化石をはじめ沢山の化石も出土している。 その中でもアンモナイトの化石などが見もの。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 光正寺古墳 全長約54m、後円部径約34m、前方部長20mで、 前方部2段築成、後円部3段築成の糟屋郡内最大の前方後円墳。 築造年代は出土品などから3世紀後半ごろと考えられ、 県内前期古墳の中でも最古期の古墳といわれている。 埋葬施設に特徴があり、5か所の埋葬施設が発見されている。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 七夕池古墳 直径29m、高さ3.7mの円墳で糟屋地区最大の円墳。 古墳時代前期末の竪穴式石室 から 木棺内に女性の遺体を安置し、 琴柱形石製品や刀、鏡、3300もの玉が出土している。 3段築成で幅3.3mの周溝が巡っている。 |
|||||||||||
| 福岡古代史探訪の旅 1福岡市内1 2福岡市立博物館 3宗像大社中津宮(大島) 4.宗像大社辺津宮 5.鎮国寺、奴山古墳群 |
|||||||||||
| 6.宮地嶽神社 7.香椎宮ほか 8.櫛田神社ほか 9.大宰府天満宮1 10. 太宰府天満宮2 . | |||||||||||
| 11.九州国立博物館2 12.大宰府4 13.大宰府5 14.宇美八幡宮 15. | |||||||||||
 |
福川タカ子のホームページ |
||
 |
福川さんちのホームパージ |
||
 |
しらとり保育室のホームページ |
||
| トップページへ | |||
|






























